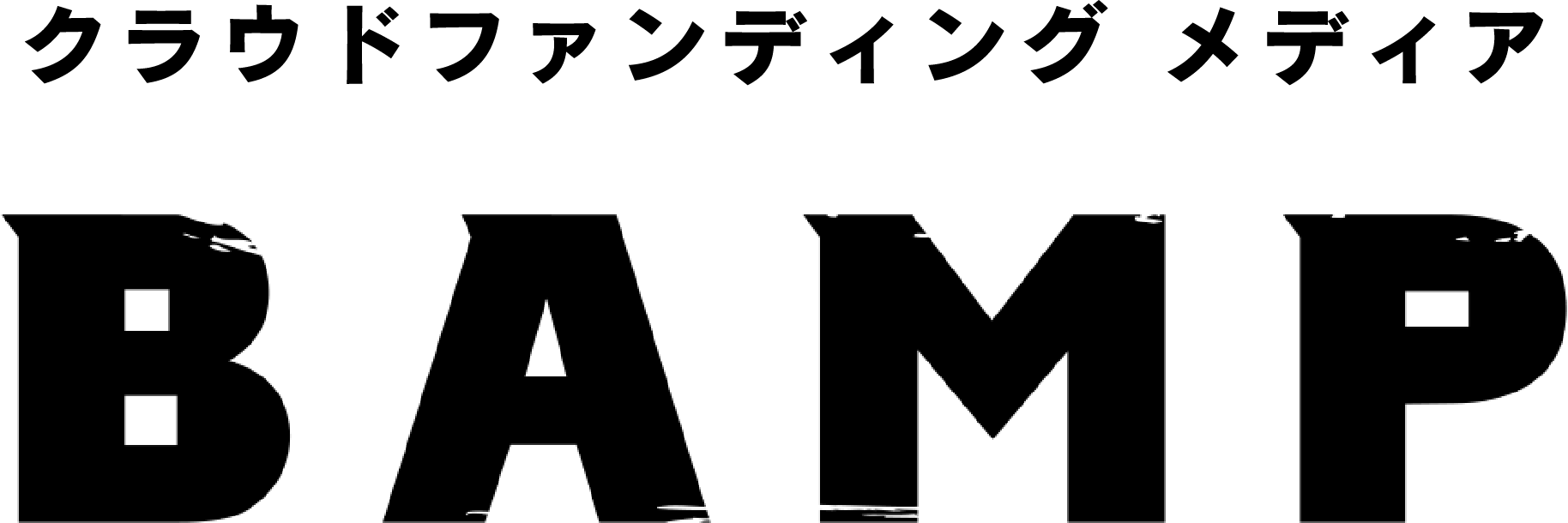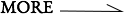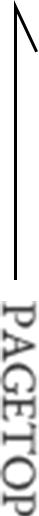日本からおよそ8700キロ。東欧の地ポーランドの国立バレエ団で、プリンシパル(バレエカンパニーにおける最高位)として踊る一人の日本人女性がいる。
海老原由佳さん、30歳。ポーランドに渡って丸6年となる彼女は、今や同バレエ団の「顔」として、クラシックからコンテンポラリーまで、さまざまな作品で主役を務めている。

はにかみながら、探り探り言葉を選んで話す、実際に対面した由佳さんはかわいらしい女性だ。一方でその経歴や語られるエピソードからは、とんでもなく「強い女(ひと)」という印象を受ける。
10代で一人海外へ渡り、世界を行脚して仕事を見つけ、さまざまな逆風に打ち勝ってトップに上り詰めたというのだから強くないはずがない。けれども目の前にいるこの女性の「可憐さ」と、語られることの「強さ」とのギャップは、一体どういうことなのだろう。
それはまるで、観衆が目にする舞台上のダンサーの華やかさと、それを可能にする隠されたアスリートとしての凄みという、バレエが持つ二面性を象徴しているかのようだ。
「一人で生きることを選んだから、ここまで来られた」と話す由佳さん。その言葉の意味することとは? ソーシャルメディア全盛の、つながることにこそ価値があるとされる時代に際立つ、異国で一人踊り続けた由佳さんの半生を聞いた。
プロフィール
海老原由佳(えびはら・ゆか)
▼フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yukaebiharadancer
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/_yuka.ebihara_/
たった一人の日本人。周りとの違いが逆風から追い風に
現在、ポーランド国立バレエ団には由佳さんを含めて6人の日本人ダンサーが在籍する。しかし、由佳さんが門を叩いた2010年当時は、今とはまったく違う状況にあった。
閉鎖的で、日本人はおろかアジア人さえ一人もいなかった。「ポーランド人の心」とも称される由緒正しい国立劇場で、外国人である由佳さんが踊ることを快く思わない人もいたという。
「そもそも、日本人として違う国で踊るっていうのがすごく大変で。見た目が明らかに違うし、ポーランドでも最初は『なぜ日本人が?』みたいな反応がたくさんありました」(由佳さん、以下同)
観客に受け入れられるかどうかという「劇場の壁」以上に、リハーサル時からダンサー間に排他的な雰囲気を感じた。レッスンは当然、すべてポーランド語。通訳してくれる人もおらず、過半数が外国人になった今からでは考えられないほどの逆風が吹いていた。
 photo: Katarzyna Milewska
photo: Katarzyna Milewska
「日本人であること」は、長らく由佳さん自身にとってのコンプレックスでもあった。まずは、どうしても超えられない骨格の壁に悩まされてきたという意味で。さらに遡れば、そもそもの「出会い」からしてそうだ。
家族とともに中国に住んでいた6歳の時にバレエを始めた由佳さんは、10歳で日本に帰ることになった際、そこで初めて出会った日本のバレエにショックを受けた。
「日本のバレエスクールの子たちは良くも悪くも、私が中国で学んできたこととは明らかに違う学び方をしてきていて、その違いにびっくりしました。職業としてもとても成立しているとはいえない日本の現実を前に、次第に『本気でバレエをやるなら外へ出ないといけない』と思うようになっていきました」
しかし、当初は逆風だった「日本人であること」は、いつからか他のダンサーにはない武器として、由佳さんをプリンシパルに押し上げる追い風へと変わったのだという。
「日本人はストイックだし、とことん極めるというか、細かいところまで作り込む。私がここまでこられたのは、そういう極める力が周りの人たちよりあったからだと思います。
海外で活躍していく上では、日本人の繊細さとかデリケートなところとかが自分にもあって、それをプラスに使うことができるということに気付けた。ああ、私にも日本の心があってよかったって。それは外に出てみて、初めてわかったことでした」
人生の選択に正解はない。だったら信じられる自分を作らなきゃ
ポーランドで踊るようになって6年。「自分の居場所がある。そのことがありがたい」と漏らす由佳さんの言葉には実感がこもっている。
18歳で念願かなってカナダにバレエ留学。そこから「ヨーロッパで踊りたい」という夢を追って、世界を舞台にしたオーディションの旅に出た。ドイツ、オランダと渡り歩いて、最初に見つけた仕事はノルウェーの国立バレエ団。だが半年の短期契約だったから、練習と並行してすぐに次の仕事を探さなければならなかった。
イギリス、フランスと拠点を移し、アメリカを経てクロアチアへ。「明日どうなるかもわからない勢い」で何も知らない国を踊り歩きながら、その日その日を生きていた。
 photo: Marek Wojciak
photo: Marek Wojciak
「毎回場所を変えるたびにゼロからのスタート。私が知っている人はいないし、私のことを知っている人もいない。まずは自分がどれだけ、どういう風に踊れるのかを認めてもらう必要があるから、毎日必死でした。
でもそうやって結果を出して、また次の場所に行くっていうのが楽しくもあったんです。大変だったけど、あのころはもう、ただただ踊りたかった。その気持ちに正直に踊っていたからこそ、結果がついてきたんだと思います」
周りはみんなライバルだし、高校の友達ももはや世界が違いすぎる。弱音を吐きたくなるような夜もあったが、泣いて親に電話することも一度もなかった。
「本当は『一人で生きることを選ぶ』なんて偉そうなこと言えないんですよ。実際、親にはなにかと支えてもらっていたし、いろいろと心配したり励ましてくれる友人はいました。ただ、本当に本当の大変なところは誰にも、たとえ恋人にも見せられなかったし、見せたくなかった。
それが一度出てしまうと、どんどん自分が緩くなってしまうと思ったから。ギリギリのところで自分と戦っていました。それはもしかしたら、本当は私がすごく弱かったからなのかもしれません」
でも……と由佳さんは続ける。
「人生って常に何かしらの選択をしないといけないものじゃないですか。そして、一つ一つは小さくても、そうした決断によって人生は大きく変わりますよね。18、19歳でどっちが正しいかなんてまったくわからないし、だから先生や親に聞くんだけど、彼らにだって本当はわからない。だってそれは私の人生だから」
最初にノルウェーの契約を受ける際には、アメリカのカンパニーからの誘いもあり、またもらえたのが短期契約だったということもあって、いろいろ助言をくれる人がいた。「もう1年バレエ学校にいて、フル契約を取れるカンパニーを探したほうがいいのではないか」といった意見を聞いて、かなり悩んだという。
しかし最終的には、ヨーロッパで踊りたいという自分の思いに従った。「その先のことは行ってから考えればよい。また何かチャンスが見つかるかもしれない」という自分の直感を信じて、オファーを受けることを決めた。
「あの時、人のアドバイスを受け入れていたら、もしかしたら今よりも幸せだったかもしれない。でもそれはどうやっても比べることができないから。だったら信じられる自分自身を作って、自分で責任を取れるようにしよう、と。
大学を辞めてバレエを選んだからには成功しないと、というのがその後もずっと頭の中にあったし、そこからは自分がしてきた一つ一つの決断を後悔しないようにと思って生きてきました。それがなかったら、ここまでやってこれなかっただろうなって思います」
「その人の人生を投影して踊るのがバレエ」なのだと由佳さんは言う。芸術家として、踊り手として、人生の背景を背負って踊る。だから同じ振り付けであっても、違う人が踊れば違うものが出来上がるのだ。
由佳さんのバレエが人種や文化の違いを超えてポーランドを魅了し続けているという事実は、周りに流されることなく、自分の人生と向き合い続けることの意味を教えてくれているようにも思える。
一人で踊る、のその先へ
自分の人生を一人で抱え込み、また「ゼロイチを繰り返すことが楽しくもあった」と語っていた由佳さんはしかし、ここへ来て心境の変化を感じているのだという。
「以前は他のカンパニーのオーディションを受けようと思ったりもしていたんですけど、同じところに長く居続けるからこそ行ける、次のレベルというのもある気がするんです」
女性ダンサーは、子供を産んで戻ってきた時が一番感情豊かに踊れると言われるのだという。今すぐにそうした選択をすることはないとしても、由佳さんが「次のレベル」というのには、例えばそうした意味も込められている。
「もちろん、身体を元に戻すのにはものすごく時間がかかるし、リスクは大きいんですけど。でも、そのくらいの挑戦が欲しい。場所を変えるだけじゃなく、自分に挑戦するというような」

photo: Ewa Krasucka
今年1月、同じカンパニーで踊るスペイン人男性と入籍したことも、こうした心境の変化に少なからず影響しているようだ。
「ポーランドに来てしばらくして、自信をなくして本当に全部やめてしまおうかと思った時期もありました。美しいポーランド人、ロシア人女性に囲まれてのリハーサルが続き、こんなに立っているだけで絵になる、身体的にも恵まれた人たちの中でどうすればいいんだろう、って感じで。最初のころは彼女たちとなかなか馴染めず、楽屋などで一緒にいるのを怖がったり、気を使ったりしていました。
そういう時にもしばらく一人で悩んでいましたが、限界だったんでしょうね。彼の存在に助けられてしまいました。それまでは自分で全部コントロールできないと嫌で、それで一人で生きてきました。けれども彼が支えてくれたことで、『もし人に寄りかかっていいのなら何が起こるんだろう』と考えられるようになっていったんです」
改めて、「自分のことだけを見つめて、自分だけのためにすべてを費やせたというのは本当にありがたい時間だった」と自身の歩みを振り返る由佳さん。ただ、同時にそれが間違いなく正しかったとは思えない自分もいるという。
「今だから気付くことですが、そういう生き方をあんまり長く続けるのは、舞台人としてはよくないのかもしれません。何かを得るためには与えないといけない。自分の本当のところを隠していたら、それ以上のモノは生まれない。そう思うようになりました。
一生懸命、死ぬ気で生きていたのが、ちょっと柔らかくなった。そのことが舞台の上でもいい影響をもたらしてくれたらいいなって、今はそう思っているんです」
すべてを自分でコントロールすべく張り詰めて生きてきた由佳さんは、彼と出会ったことで生活のリズムや精神的なバランスを変えてみた。それは彼女にとって、ぼくらが想像するよりもずっと大きく、勇気のいることだったろう。その彼女が新しい歩みを始めようとしていることに重みがあるし、意味があると感じる。
「つながりの価値」がことさらに強調される時代。それ自体に間違いはないとしても、一方には孤独を受け入れた人にしか出せない輝きも確かにある気がするのだが、皆さんはどう思うだろうか。
「CAMPFIRE」でクラウドファンディングに挑戦しませんか?
「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」は、誰でも無料でカンタンに資金調達に挑戦できる国内最大のクラウドファンディングです。