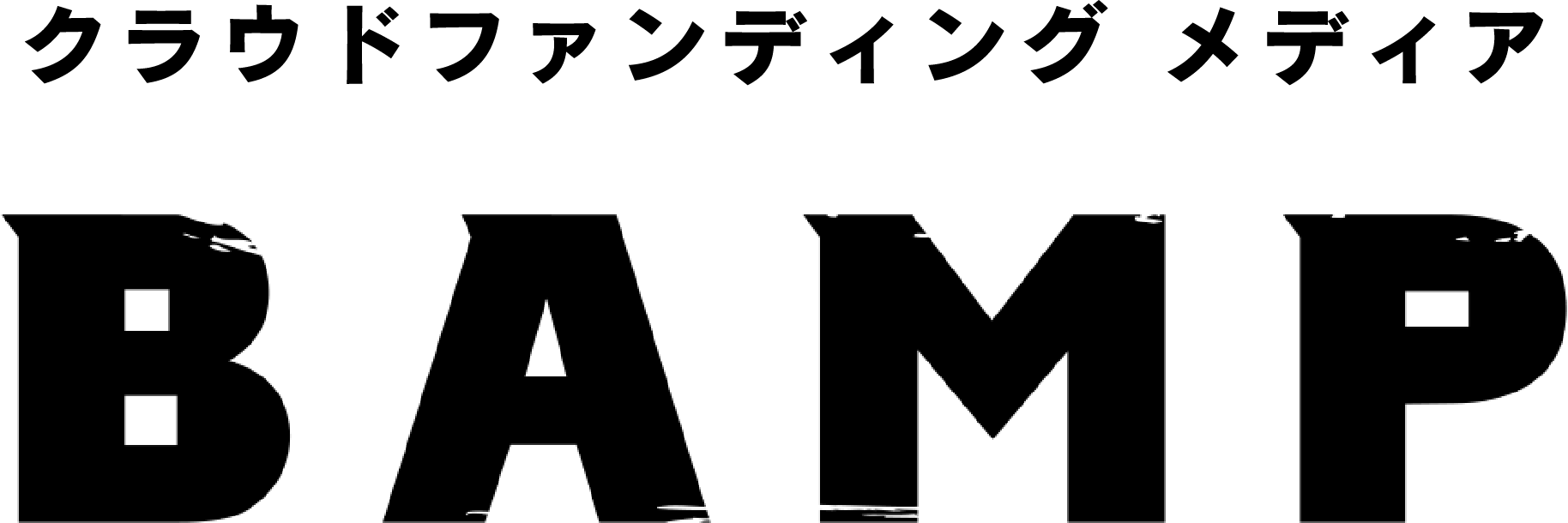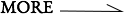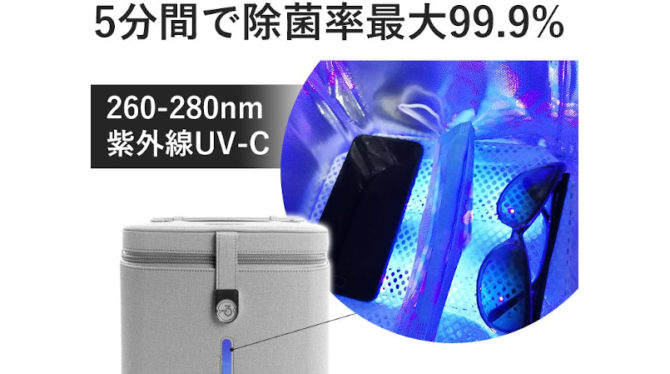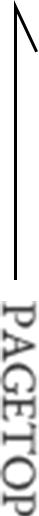たったひとりでリスクをとり、責任をとり、決断をし続ける人々、「経営者」。
彼らを見ているうちにふと気づいたことがある。
それは、わたしの中にも小さな「経営者」がいるということだ。わたしたちはみんな多かれ少なかれ、自分自身の経営者であり、自分の人生という事業を営んでいる。
世の経営者が会社から逃げられないように、わたしたちもまた、自分の人生からは逃げられない。鎧をかぶってこの平坦な戦場を生きぬかないといけない。わたしが経営者に惹かれるのは、きっとそれが拡大化・社会化された存在だからなのだと思う。

加藤さんと初めて出会ったのは、今から14年前。
加藤さんが30歳、わたしが19歳のときだった。
始まりは、『SCRAP』というフリーペーパーだった。
編集部は京都にあって、2か月に1度発行されているその雑誌は、表向きは音楽のフリーペーパーと名乗っていたけれど、実際にはおもしろければなんでもありな特集を組んでいた。
初めて手にとったのは2号で、特集はラジオ。表紙にマンモスの絵が描かれていたことも覚えている。
その編集後記を読んだとき、わたしはすぐ、
「自分もこういう文章を書けるようになりたい」
と思い、ボランティアスタッフに応募した。
その文章を書いていたのが、『SCRAP』の編集長である、加藤さんだった。
彼の文章は、「伝えたいことがある人の文章」だった。
誰かの代弁でもなく、誰かに褒められるためでもなく、ただ自分が伝えたいことを率直に書いた文章。
だからこそ、彼の文章はとても自由だった。
わたしが書きたいのはこれなんだと、19歳のときの自分は感じとったのだと思う。

2004年に創刊されたフリーペーパー『SCRAP』。第1号の特集は「MUSIC SMILE in KYOTO」
『SCRAP』は、創刊してすぐわたしのような若者を複数惹きつけたらしい。
初めて訪れた編集会議には数名の大学生がすでにいて、みんなが次の特集についてのアイデア出しをしていた。
そこはとても不思議な空間だった。みんな、ただ「おもしろそうだから」という理由でそこに集まっていて、それ以外に目的も何もないといった顔をしていた。
その中心にいた加藤さんは、背が高くて、めがねをかけていて、飄々とした雰囲気の人だった。
文章を書いたり、企画を考えたり、イベントをやったり、バンドでギターを弾いて歌をうたったりしながら暮らしているのだと言っていた。
「この人はどうやって食べているんだろう?」というような大人がたまにいるが、加藤さんはまさにそういう人だった。
「君は何がやりたくてここに来たの?」
初めて出会った日、加藤さんにそう聞かれた。
「文章が書きたいんです」
緊張しながら答えると、加藤さんは、
「じゃあライターやな」
と、あっさり言った。
「まあまずは書いてみて。わからんことあったら、聞いて」
人に読んでもらうための文章を書き始めたのは、このときからだ。
それから約2年間、わたしは加藤さんに教わりながら、『SCRAP』でいろんな記事を書いた。インタビュー記事、レポート、CDレビュー。時にはポエムも書いたりした。
頼まれても頼まれなくても、何でも書いた。
そのたびに加藤さんに読んでもらって、「ええんちゃう」とか「ここはもっとこうしたら」とか言われた。今読めば癖だけが強い拙い文章だったと我ながら思うけれど、それについて加藤さんに何か言われたことはなく、ただ「伝わりやすくするにはどうしたらいいか」、そして「伝わったらどんなことが起きるか」を教えてくれた。
「お前はもっと書けるようになるよ」
と言われたときには、本当に嬉しかった。
加藤さんはわたしにとって、初めて「書くこと」を教えてくれた人なのだ。

2008年、加藤さんは株式会社SCRAPを立ち上げた。
そのときには彼はもう「リアル脱出ゲーム」というアイデアを思いつきイベントを行っていて、大手広告代理店から引っ張りだこ。次第に東京と京都の二重生活が始まり、3年後には拠点を東京に移していた。
現在株式会社SCRAPは、国内外合わせて18か所に店舗を展開し、アルバイト含め2000人規模のスタッフを抱えるまでに大きく成長。
加藤さんはその会社の経営者として、そしてクリエイターとして、今も活躍を続けている。
「リアル脱出ゲーム」は会場に集まった参加者同士で協力しながら、数々の謎を解いて脱出する体験型エンターテイメント。東京ドームや六本木ヒルズなど様々な場所で開催され、現在までに550万人を動員。海外での人気も高い
この『経営者の孤独』という企画が立ち上がったとき、インタビューする相手として最初にわたしの頭に浮かんだのが、実は加藤さんだった。
師匠のように、先輩のように、戦友のように、かつてわたしに「書くこと」の喜びを教えてくれた加藤さん。
気がつけばわたしは、あの頃の加藤さんの年齢を追い越していて、「書くこと」でなんとか食べられるようになっていた。
もしあの頃の加藤さんと今のわたしが出会っていたら、さまざまなことを同じような立ち位置から語り合っていたんじゃないだろうかと思う。
そんな妄想をしているとき、ふと思ったのだ。
今なら「あの頃の加藤さん」と「今の加藤さん」を書けるんじゃないかなと。
なんとなくで、根拠はない。
ただ、わたしは彼に、率直に聞いてみたかった。
「加藤さん、あの頃と今と、何か変わりましたか?」
その質問の答えに、彼の“孤独”が垣間見えるような気がしていた。

久しぶりに会った加藤さんは、相変わらず背が高くて、めがねをかけていて、飄々とした雰囲気をまとっていた。
その日の取材のあとにはライブハウスで弾き語りライブもするのだと言っていて、以前とあんまり変わっていないなと思った。
でも、加藤さんは、この10年間、経営者として走り続けてきたのだ。
その距離だけ、そのカロリーだけ、遠いところに辿り着いている。
わたしはそんな「今の加藤さん」のことを、ほとんど知らない。
「お久しぶりです。今日はよろしくお願いします」
そう挨拶すると加藤さんは、
「ご活躍されてるようで何より。インタビューしてもらえて光栄です」
と冗談っぽく言った。
わたしは笑いながらも、なんだか緊張してしまう。
まるで「文章が書きたいんです」と言った、出会った頃と同じように。
プロフィール
加藤隆生
毎年「これが最後かな」って思っていた

SCRAPが会社になってから、昨年で10年が経ったんですね。
そうだね、10年経ったね。
事業内容について、改めて聞かせていただけますか。
リアル脱出ゲームの制作と運営が売り上げの大半かな。グッズ販売したり、広告を作ったり、本を出版したりもしているけど、やっぱりそれがほとんどだね。
じゃあこの10年、もっぱら「謎を作る」ことがお仕事だったという。
そうじゃない? 謎まみれだよ、もう。
会社としては、今どんなフェーズにあるんでしょうか。
いやお前、フェーズって。そんなのわかんねえよ。
えっ。
来年急降下するかもしんねえし、来年急上昇するかもしんねえし。それは全然わかんない。だから、ずっと僕は社員に対して「うちは今年で終わりだから」って言い続けてきているんだよね。
「今年で終わり」?
うん。少なくとも6,7年目までに入った社員には、全員に「うちは来年潰れるかもしれない会社だから、それでいいなら入っておいで」って言ってた。
それくらい、先が見えない仕事ってことですか。
まあ、エンタメだからね。自分たちがどれだけ「価値がある!」って言ってても、世の中の人が公演のチケットを買わなかったら価値がないってことだから、いつどうなるかわかんねえなって。だからずっと「ブームだブームだ」って言われてたとしても、毎年これが最後かなってつもりで取り組んでたよ。

「うちは今年で最後かも」って気持ちは、今もあるんですか?
ずっとそういう気持ちでやってきてたけど、実は3年くらい前から「これはひょっとしたら続くんじゃないか?」って思ってきたんだよね。
へえー。
会社も7年経つとさ、10周年が見えてくるじゃん。てことは10年間やり続けた筋肉がついたってことだから、20年目が見えてきちゃうわけだよ。もちろんエンタメなんて社会情勢によって一番最初に切られるものなんで、どうなるのかなんてわからないけど、少なくとも10年間継続させるだけのメソッドっていうのは体の中に蓄えられている。「これもしかすると20年続くかもしれないな」ってときに、「それなら20年続くやり方が必要だな」って思って、働き方改革が社内でゆっくり始まったって感じかな。給与制度も、最近になってようやく整ってきたし。
あ、そうなんですか。
うん。それまでは、儲かったら「儲かったぞー!」ってボーナスどーんと出す!みたいな。「ボーナスすごいだろ!」「すごいです!」「次もがんばろうな!」「がんばります!」っつって、できあがった綿菓子をちぎって投げつけるようにボーナス出してたんだよね。それで、「ふー、なくなったー」みたいな。
投げつけるように(笑)。
そう。儲かればボーナスの額は倍々ゲームみたいに増えるから、年収は増えるんだけど、給与制度の基盤がちゃんと整ってなかったんだよね。そこをちゃんとしようと。
でも、「謎」をつくる仕事って、時間給で換算するの難しそうですね。
そうなんだけど、うちの社内にはここ何年かで、アイデアを出す人よりも、アイデアを形にする人のほうが増えたのよ。僕らは東京でおもしろいものを一個作ればいいけど、形にする人は日本全国、海外にだってそのアイデアを持って形にしていくわけだから、このままの給与体系じゃだめだなと。だから最近になって、働き方を見直しているんだけどね。
一発当てたがゆえの、悲しみとか不安

なるほど。でも、「続くかもしれないな」って思い始めたのは、つい最近の話なんですね。最初の頃は、これで一生食って行こうっていう感じじゃなかったんですか。
いやもう、ぜんっぜんなかった。なんなら、なるべく早く稼いでとっとと逃げよう、みたいに思ってたよ(笑)。
あはは。そうなんですか。
一生食える分稼いで、なんとか俺ひとりだけでも撤退だ!みたいな気持ちが、数パーセントはあったと思う。いや、でもそれは、「あった」というか「あらざるをえなかった」んだよね。俺、それまで知らなかったんだけど、どんと儲かっても、税金で持ってかれるのね。京都のインディーズミュージシャンからしたら、年収1千万なんてとてつもない額だから、一生食っていけるのかな?って思ってたんだけど、周りやメディアがわあわあ騒いでいる割に、東京で子供食わせながら生活していくってなると、そんなに大したアドバンテージじゃなくて。
へえー。
リアル脱出ゲームがばーん!って売れて、みんなが「加藤さんすごいですね!」って接してくる空気の中、むしろ自分ひとりだけ、京都のインディーズミュージシャン時代よりもぎらついていた感はある。金銭的な部分で言うと、世の中の評価と自分が一致していないなって思ってた。でも、もちろんその逆もあって、これだけしか働いていないのにこんなにもらっていいのかよっていう気持ちもずっとあったんだよね。一発当てたがゆえの悲しみとか、不安みたいな。
一発当てたがゆえの不安。
一発当てたことによる喜びみたいなのはありつつも、「この一発がいつ終わるんだろう」っていう恐怖や、二発目を当てることの難しさと戦ってたりもして。その状態で、最初の5、6年はやってたかな。
だから「今年で終わるかもしれない」って思っていたんですね。
そう。でも、「一発屋」と言いつつも、俺はそれが10年続いている状態なんだよ。
ああー、確かに。
「何作ったんですか?」って聞かれたら、「リアル脱出ゲームです。以上」って、そういう意味では一発屋なんだけど、俺が作った「一発」っていうのは実はジャンルだったってことに、しばらく気がつかなくて。
なるほど。加藤さんは、「リアル脱出ゲーム」というひとつのジャンルを作ったんだ。
そう。世の中の定義で言う「一発屋」って、一冊の本やひとつの曲が当たりましたってことなんだけど、俺の場合は「リアル脱出ゲーム」というジャンルだった。その枠組みの中で、300本以上の企画とプロジェクトを作っているんだよね。その中で赤字を出したのって、実は2本だけしかなくて。
すごい。ほぼ全部成功させているんですね。
この10年間、何本もクリエイティブで成功させてきたという点で言えば、こつこつ努力してきたヒットメーカーとも言えるのよ。
だから、続くんじゃないかなと思い始めたと。
そうだね。
でも、リアル脱出ゲームを思いついた衝撃、心の揺れっていうものはまだ覚えてるんだよ。あのときひとつの大きな「枠」を思いついた。それに当時は気づいていなかったけど、ものすごい衝撃だったんだよね。あのときの衝撃みたいなものを、もう一度体感したい気持ちはある。だから、もう一度あの衝撃を感じるために「一発屋」と自分のことを思ってるね。

加藤さんはもともとゲームが大好きで、当時インターネット上で流行っていた「脱出ゲーム」も1プレイヤーとして楽しんでいた。
その「脱出ゲーム」を現実世界でやったらどうなるか?
そんなアイデアが出たのは、フリーペーパー『SCRAP』の編集会議中だったという。
『SCRAP』は特集と連動して毎号必ずイベントを行うフリーペーパーだったのだけど、このリアル脱出ゲームイベントは最初からものすごい反響があったらしい。
そのときにはわたしはすでに『SCRAP』にはいなかった。
加藤さんたちが思いついたリアル脱出ゲームがヒットして、みるみるファンがついて、ビジネスとして大きく育っていくのを、少し離れたところから見ていた。
わたしには、加藤さんも『SCRAP』も急激に変化したように見えていた。
作るものが「フリーペーパー」から「リアル脱出ゲーム」に変わって、「フリーペーパー」ではなく「リアル脱出ゲーム」で『SCRAP』を知ったというスタッフもお客さんもどんどん増えていった。
それは、これまでになかった勢いとスピード感だった。
「当たる」「成功する」というのはこういうことなのかと、わたしは加藤さんの件で初めて目の当たりにした。
そんな急激な変化の中で加藤さんはどんなことを感じているのだろうということを、ずっと聞いてみたかった。
作りたいものと、求められるものは、一致していたのだろうか?
加藤さんの中で、「何か違う」というのはなかったんだろうか?
わたしは、どきどきしながら質問を重ねる。
一方で加藤さんは相変わらず、淡々と自分の言葉で話し続けるのだった。
成功しても、舞い上がり方がわからなかった

リアル脱出ゲームでばーんと売れたとき、加藤さんは一気に環境が変わりましたよね。その加藤さんと、それまで京都で音楽やフリーペーパーを作っていた加藤さんで、乖離を感じたりはしなかったですか?
それはない。全然地続きだったね。
わ、即答なんですね。
うん。「変わっちゃったね」って言われたこともないと思う。自分でも、変わったところもほぼないと思うし。音楽作っているときだって、仲間を集めて、こつこつ時間をかけて、わあわあ言いながらものを作ってたから。その作り方の本筋自体は変わっていないんだよね。ただ作るものが、曲からゲームに変わっただけで。……あと俺、売れる前から偉そうだったしね。
それは……そうでしたね(笑)。
自分でも思うよ。なんで何の実績もないのに、あの頃の俺はあんなに自信満々だったんだろう?って。その件に関しては俺も不思議なんだけど。でも、売れる前から感じ悪かったおかげで、売れてから「あいつ感じ悪くなったな!」っていうふうには、ならないですんだんだよね(笑)。あと、うまくいきだしたのが36歳とかからなんで、「すごいですね」って言われる頃には舞い上がるような年齢でもなかったし。それに、舞い上がり方がわからなかったの。
舞い上がり方がわからない?
普通さ、IT業界とかで成功して舞い上がった人って、舞い上がった先輩がいるじゃん。舞い上がり方のテストケースみたいなのがあるのよ、周りに。
例えば、綺麗な女優さんと付き合うとか、いい車に乗るようになるとかですか。
とか、高いお店に行けるようになるとか? そういう「成功」のわかりやすい象徴みたいなのがなくて。僕の周りには。だって、「謎業界」っていうのがこれまでになかったからね。当時はひとりだけ「謎業界」でぽつんと成功してて、先輩もいないし、後輩もいないし。ばーんとヒットして、テレビにも出た、雑誌にも出た、全部の新聞にも取材された、お金だってそれなりに入ってきましたっていう、この状況の利用の仕方がわからなかったというか。それに、そういうのを自慢する奴が死ぬほどダサいってことも知ってるじゃないですか。そんなダサい奴らとポジション的には一緒になったので、なんか「控えねば」みたいな。
(笑)
まあ、でも、そのイライラはあったよ。「俺は山の上に行って、そこでもっとちやほやされるんだ!」って思いながら、一所懸命登ってばーんと登りきったら、そこでは別にパーティなんて行われていなくて、ただ次の山道が続いていて。「あれ、これまだ続くの?」みたいな。『情熱大陸』に出たらゴールじゃないの? 綺麗な子指差したら誰とでもヤレるんじゃないの?って思っていたのに、世の中は俺を無視し続けたんだよ。
誰とでもヤレるかはわからないですけど(笑)、そんなに変わらないものですか?
僕のまわりは粛々としたもんでしたよ。だって俺、「モテるんじゃないかな」と思ってキャバクラ行ったもん。そこで必死に言ったよ。「俺、『情熱大陸』出たんだよ」って。そしたら「へえ、ところでボトルは入れないんですか?」みたいな。そこで「えー!?」ってなって(笑)。
あははは。
『情熱大陸』に出たのにお金使わないとモテないの!?って、そのときなんらかの真実に気がついた気がする。

さっき「自分は変わっていないし、全部地続きだ」っておっしゃっていましたけど、作るものは変わりましたよね。加藤さんにとっては、音楽やフリーペーパーを作ることも、謎を作ることも、全部やりたいことだったってことなんでしょうか。
うーん。「やりたいこと」というよりは「やれること」だよね。別に俺は、「ミュージシャンになるんだ!」とか強いこだわりがあったわけじゃないし。その場その場で興味があることを、必死でやってただけで。
じゃあ、もともと「ミュージシャンとして食っていこう」って気持ちが強かったわけではない?
いや、それはあった。だって、食っていかないといけないわけじゃない。その「食う方法」として、今のところ音楽が一番評価されているなって思ったの。それと同時に、ブログを書いたり、雑誌を作ったり、ラジオをやったり、広告を作ったり。そういうのを、ずっと並行してやっていたんだよね。そこには、自分が何かアクションを起こすことによって、世の中が良くなったらいいな、そしてその結果自分が生活できたらいいなっていう気持ちしかなかったんだよ。その中で一番確率の高いものとして、音楽というのが重要なファクターであっただけって感じかな。だから、何が何でも音楽でやってくぞ!って訳ではなかったんだよね。
ではその「食う方法」の中にぽんと謎が入ってきて、それがファクターとして大きくなったという?
そうそう。自分がやっていることの中で、世の中から求められている比率に応じて力を入れるっていうのは自然なことだったね。「俺の本来の職業はミュージシャンなのに、リアル脱出ゲームでこんなに売れてていいのか?」っていう、葛藤はなかったと思う。自然な流れだったし、そこには何か決断した記憶すらなかったな。だから戦略的であったわけでもないよ。言われるがままにやっただけ。
何かを諦めたわけでもない。
うん。
経営者としてよりクリエイターとしての不安の方が強い

加藤さんって、会社ではどういう仕事をされているんですか? 役割というか。
一番やっていることは監修かな。SCRAPという名前のもと世の中に出ているものすべての、クオリティチェック。それから、やるべき案件を決めることもそうかな。数々の案件の中で、会社として今どれを一番やるべきか、やらざるべきかを決めている。あとは新しいプロジェクトにがっつり関わるって感じ。それくらい? だから暇だよ、俺。
暇なんですか。
うん。時間余っちゃってるから、バイトとかしたいもん。Uber Eatsとかで。
(笑)。会社には毎日行っているんですか?
行くけど、6時間とかだよ。最近はもっぱら『ダンガンロンパ』っていうゲームをやってた。
ああ、加藤さんの場合、エンタメも仕事ですもんね。流行りも知っとかねばならないというか。
よく言えばね。あとはなるべく人と会うとか。まあ……『経営者の孤独』ってほどじゃないけど、「何してもいいよ」って言われる悲しみはあるかな。「自由」ってのがいちばん困る。結局人間って怠惰な生き物なんだよ。放っておかれて頑張れるかって言ったら、やっぱり難しい。だから、一所懸命かっこいい言葉を探してみたけれど、今はただ、怠けているんじゃないですかね。
怠けている……。それは意図的に?
いや、強い意志で怠けてるわけじゃないよ。単に怠け者だからだよ(笑)。昨年、割とでかいギャンブルを打ったんですよ。歌舞伎町のビルをほぼ一棟借りて、そこに「東京ミステリーサーカス」っていう「謎」のテーマパークを作ったの。それはかなり大きなギャンブルだったんだけど、そのギャンブルに1年をかけて大きく勝ったんだよね。だから今は一息ついているところで、また一個円熟したなっていう。細かい改善点は山ほどあるけど、今は会社全体をささやかな達成感が包んでいる時で。だから、落ちついているんだよね。誰かの作品にものすごく興奮したり、心がかき乱されることもないというか、からだがそれを望んでない。そういう時期ってあるんだよね。あと数ヶ月もたてば、ぴりっとするかなって思う。
なるほど、達成感。
それで今、経営的にも安定していて、何か新しいことにお金を突っ込むことだってできる状態だし、切羽詰まってないんだよ。でも、だからこそ、今何かを思いついてやっておかないとっていうのは思う。また次にしんどい波が来た時に、ふたつめの刀が用意できているっていうだけですごく良いことだから、何か思いついておきたいなって。でも、そういうのって切羽詰まってないと出てこないじゃん。そこに関しての不安はある。大丈夫かなって。
このまま怠けてちゃだめだな、みたいな?
うん、そうだね。でもその不安は、「自分が物を作る人間として日々腐っているんじゃないか」っていう不安かな。いいのかな、この刀を研いでなくて?って。それこそ「今年で終わるかもしれない」って思ってた数年前までは、何か物を作る時間っていうのが1日に14時間くらい確実にあったんだよね。しかも、年に360日くらい働いていてさ、それが楽しくてしかたなかったの。というか、それくらいしないと追いつかなかったし、眠くなんてならなかった。必死で仕事してて、頭動いてない時間なんてなかった。でも、今はそうじゃない。そんな今の自分の状態に対して、「これはクリエイターとして適しているのか?」という不安感はある。だけど、経営者としての不安はさほどないんだよね。
それは、何でなんでしょう?
「会社」を自分の作品だと思っていないからね。もちろん、うまくいくと嬉しいけど、うまくいかなくても「まあ俺のせいじゃないよな」みたいな(笑)。でも、自分の作った作品が売れなかったら、俺のせいだなって思う。
そうなんだ。加藤さんにとっては、クリエイターとしての不安のほうが強いんですね。
うん。そっちの方が、断然強い。
それは意外でした。経営者としてたくさんのスタッフを率いる立場で、もしも会社が立ち行かなくなったら……という責任とか不安とか、そっちのほうが大きいかと思ってました。
俺は、「経営によってなんとかなる部分っていうのは、果たしてどれくらいあるんだろう」って思うのよ。結局、良いものを作り続けて、世の中の人たちを驚かせて、この公演には絶対に行ってみたい!ってお客さんに思わせる回数がうちの会社の生命線なのに、僕が会社の業績の数字をじっと見て、「よし。来年から消しゴムの仕入れを2パーセント減らそう!」とか言っても、別になんかね……。そんなことは、もっと得意な人がいっぱいいるので。うちの社内にも。
じゃあ加藤さんの仕事は、やっぱり「作る」ことなんですね。
うん。やっぱり僕は、自分がすごく喜びたい。すごいことを思いついて、まず自分がびっくりして喜びたいし、自分がびっくりして喜んだもので、人がびっくりして喜んだらいいなって。そういうことのほうが、「経営」より優先順位が高いんだよね。
「加藤さんは、アイデアだけを愛している」

あとは、僕は社会人としては全然うまくやれなかったから。新卒で入った会社を、1年半も経たないで辞めてるし。だから、「よその会社ではおそらくやっていけないだろうな」って人も働けるような会社にしたいという理想はある。何ていうか、そのために会社としての佇まいみたいなものを、僕が一個一個緩めて行く感じかな。
緩めていく。
「優秀である」という言葉の意味が変わってほしいと思ってるんだよね。世の中で言われる「優秀」じゃない人も働けて、成果を出せて、世の中から評価される、みたいな。自分はそういう場所であるための防波堤になっている感じかな。
それは、若かりし頃の加藤さんがモデルなんですか?
いや、それもあるけどさ。あんたもそうだけど、京都で『SCRAP』っていうフリーペーパーを作るぞって言って、ばっと集まってきた人の中には、「こいつやべえな」みたいな人もいっぱいいたわけじゃない。
あはは。そうですね。
でも、そういう人たちがいまだに僕と一緒にものづくりしてたりとか、一緒に遊んでたりとか、こうして取材してくれたりとかするわけだよね。それがやっぱり嬉しいし。なんていうか、俺にとっては、今見えているその人の能力みたいなものは、10年経てば全然関係ないって思うんだよ。「自分の中に湧き上がってきたものときちんと接して、形にして、世に問うというのは楽しいことでしょ?」って言い続けていきさえすれば、割とみんなちゃんとした物を作る。
はい、はい。
そういう、人がクリエイターとして成長するための方法論が、僕の中ではあるんだよね。
なるほど。
あと、たとえば文章書くとかって根気がいるけど、アナログゲームって一発のアイデアでガラッて変わったりするから。毎日8時間働いて、毎日ブレストに参加しているとしたら、誰でも1本くらいヒット打つんだよね。そのヒットがさ、5本あると1本くらいホームランになったりするのよ。
へえー。
俺が「おもしろいなあ」って思うのは、特別何か凄い人っていうわけじゃなくて、じっとしている佇まいが感じいいなとか、コンビニで買ってくるお菓子が毎回ちょっとおもしろいなとか、その程度のことなの。その程度のことで、全然期待して待っていられるというか。まあなんか、うちの会社がそういう場所でありたいなっていう気持ちを、強く持っているんだと思う。
あの、わたし、大学時代に『SCRAP』の編集会議に出ているとき、加藤さんって会議の時にいいアイデアが出ると、めっちゃ嬉しそうな顔するなーって思ってたんです。
ええ、そう?(笑) まあでも、そうかも。
編集会議って言っても、「何でもいいから最近おもしろかったこと話して」って、みんなでわいわい話す感じなんですけど、そうしていたら入ったばかりの子とか、普段あんまり話さないおとなしい子とかが、ぽろっと何か言ったりする。そのアイデアがおもしろかった瞬間の衝撃みたいなのを、わたしはあそこで初めて経験したんですよね。
へえー。
これまでスタッフとして長くいたからとか、真面目にやってきたからっていう実績や人間関係を、一個のアイデアが簡単に飛び越えてしまう瞬間っていうのがいっぱいあったんですよ。だからわたしはあのとき、「加藤さんって、人じゃなくてアイデアしか見てなくない?」って思ってました。アイデアしか愛していないっていうか。
あははは。
それで心が折れることもあったけど(笑)、でもその分、アイデアの力の凄さを知りましたね。「アイデアひとつで、加藤さんがこんなに嬉しそうに笑うんだ」とか。
いや、それはそうかもね。フリーペーパー作ってたときに、「私はここに2年もいるのに、昨日入ってきたあの子がページもらった!」みたいな不満が、スタッフの中にうっすらあったのも気づいてはいたんだよ。今となってはビジネスなので、さすがにアイデア一個だけじゃ形にならないから、ぽっと入ってきた人がメインのディレクターになるのは難しいんだけど。とは言え、「あのアイデア考えたの、お前だよな。形になって嬉しいな」みたいな気持ちは持ってる。だから、アイデアだけを愛しているというのはまあ、そうかもしれないよね。

『SCRAP』の編集会議中にいいアイデアが出たとき、加藤さんが必ずとる仕草があった。
ばっと立ち上がり、「それや!」と言って、アイデアの発信者めがけて指を差す。
その瞬間は、みんなぽかんとしている。その中で加藤さんだけが、とても嬉しそうに笑っている。
正直に言うと、わたしは大学生の頃、そんな加藤さんがこわかった。
「この人、本当にアイデアしか見てないんだな」と思った。
そのアイデアの出処はどこでもいいし誰でもいい。ただ、心を打つアイデアさえ生まれたらそれでいい。
加藤さんはみんなに分け隔てなく優しかったし、「やりたい」ということを止めることも、何かを強いることも一切なかったけれど、生粋のアイデア至上主義者だった。それがわたしには非人間的なように思えて、なんだかこわかったのだ。
そんな彼といた時間は、アイデアの持つ力の凄さをまざまざと教えてもらう経験でもあった。
だけど話を聞きながら、加藤さんは知っていたのだな、と思った。
アイデアがすべての源だということ。アイデアがなければものはつくれないということ。
そして、アイデアはすべての人のなかに埋まっているのだということを。
だから彼は、「よその会社ではおそらくやっていけないだろうな」とか「こいつやべえな」みたいな人も受け入れる。
彼はアイデアだけではなく、アイデアの生みの親である「人間」そのものも信じていたのかもしれない。
「『自分の中に湧き上がってきたものときちんと接して、形にして、世に問うというのは楽しいことでしょ?』って言い続けていきさえすれば、割とみんなちゃんとした物を作る」
確かに加藤さんは、昔からなにも変わっていないのかもしれない。
「あのアイデア考えたの、お前だよな。形になって嬉しいな」
わたしもまた、加藤さんにそう言われて育ってきた人間だから。
「そこで稼いだ分、全部突っ込んでください」

加藤さんは、経営者としてストレスを感じたり、悩んだりすることってあるんですか?
それはあるよ。特に最初の7、8年は、責任を全部ひとりで抱え込んでいたしね。「株式会社SCRAP」という社名と「加藤隆生」という僕の名前が、同じくらい有名な時もあったし。いろんな意味で自分の中に責任を抱えていて、それを全うするための不安感はすごく強くあった。実際、孤独だったとすら思う。誰にも相談できないじゃん。
先輩もいないし。
うん、先輩もいないしね。たとえば、2017年にはお金を集め始めたんですよ。2018年に、さっき言った歌舞伎町のテーマパーク「東京ミステリーサーカス」をどーんとやるために、銀行からお金を借りたりしたんだよね。そうすると、保証人として社長の名前が書かれるわけじゃん。借りる額が数千万とかなら、失敗してもまだ返せるかなと思うけど、そのときは10億にも近いような金額だったからさ。その金額見ながら、「せっかくこの数年間コツコツと成功者感のあるようにふるまってきたのに、これ失敗したら全部飛ぶんだな」って。僕の財産や資産、すべてなくなるかもしれないプロジェクトに、今から乗り出すんだっていうことへのヒリヒリ感だよね。そういうときに家で娘の顔とか見ていると、こいつが笑ってられるのもいつまでかなあ、みたいな不安感もあって。嫁にその話をしたら、ある夜帰ったときに置き手紙があって。「いざとなったら私も働くので、自分が信じた道を進んでください」って書いてあって、ちょっと泣いたりして。じゃあ行くかって、そこに突っ込んでいったんだけど。
ああ……。
……うーん、なんか、今思えばこれまで順風満帆だったかのように見えるんだけど、でも冷静に考えてみたら、全突っ込みのギャンブルをずっとやってきたんだよね。たとえば、10の小屋で当てて、10儲かりました。じゃあ次、100の小屋でやりますってときに、「そこで稼いだ10を全部突っ込んでください」って言われんのよ。で、「ああ、はい」って言って、10突っ込みました。100稼ぎました。じゃあ次200のところでやるときに、「さっき稼いだ100全部突っ込んでください」って言われる。そういう全突っ込みのギャンブルを、これまでに30回くらいやらされたって感じがあって。今振り返れば、その30回の勝負を俺は30連勝したんだなってことになるんだよね。
それは……すごいことですよね。
いやこれもう、伝わるかどうかわからないんだけど、感覚として言うと「9割勝つギャンブル」なのよ。「まあ今ここにある金全部突っ込んでも、おそらく9割は勝つな」って感じなの。それで、「はい、勝ちました。じゃあ次は東京ドームでやりましょうよ」「遊園地貸し切りましょうよ」「お客さんみんな求めてますよ」ってなる。で、こっちは「いけるかな?」「まあ9割はいけるか」「じゃあ全部突っ込もう」「また勝った」って感じなんだけど、9割勝つギャンブルを30回やったらやっぱりだめなのよ。だって、10回に1回は負けるんだから。
ああー。
これはどっかでだめになるなってずっと思いながら、最初の3,4年はやってて。生きた心地はしてないんだけど、おもしろくて楽しいからリスク管理みたいなのが麻痺してて、普通の状態ではなかったよね。それがどこからか、全部突っ込んで「はい勝った」っていうときに、「次は半分でいいですよ」って時期が来る。店舗を作って、そこが安定した利益を作ってくれるようになったときに、そういうふうに事情が変わってギャンブル性が薄れてくるんだけど、それから何年も経って会社が育って、人が増えて、知名度も上がってきた中で、また借用書を前にしてさ。そのとき、「あ、また俺、会社つくった頃と同じひりひりした思いをしないといけないポジションなんだ」って。
……。
でも今のままやってたら、確実にズルズルと下がっていく。いや、エンタメってズルズルと下がるんじゃなくて一気に下がるから、それが嫌なら仕掛け続けるしかなくて。今この状態で、俺はまだ仕掛け続けなくちゃいけないんだなって。しかもそれを、俺が心の底から望んでいるわけでもないんだよね。世の中や社会の要請もあって、もちろん自分も9割勝つって思っている。だけど、まだその感覚でやらないといけないんだっていうことへの不安感。そしてその不安感を誰とも共有できないんだなっていう、孤独はあったね。

その不安とか孤独っていうのは、凄まじいものだと思うんです。もしかしたらすべて失って、とんでもない借金をひとりで背負うかもしれない。だけど、それでもやっていけたのって何でなんですか。その感情と、どう付き合ってきたんでしょうか。
いや、でもさ。とは言え「9割は勝つ」んだよ。どっかで「まあ大丈夫だろ。だって9割だよ?」って気持ちがある。でも、かと言って不安が消えるわけではない。負けたら恥ずかしいだろうなあとか、負けたときのリスクがでかすぎるなあとかね。そんな気持ちだから、どう付き合うかというよりは、打ち消すっていうか、なるべく9割のほうに心を持っていくって感じだよね。時折、不安がハッとやってくるわけよ。ドラマで倒産した社長さんが銀行に頭を下げているシーンとか観ていると、「ああ〜、やめてやめて!」みたいな。それ観ながら、「でもこの人たちも9割勝つと思ってお金を借りたんだろうなあ」って。失敗すると思ってお金借りる人なんて、いないからね。だから僕は、なるべくそっちのほうに心を置かないようにしたし、家族にもオープンにするようにした。いろんな人に話をしに行ったりもしたよ。レベルファイブの日野晃博さんとか、ドラクエを作った堀井裕二さんに話をしに行ったり。で、そこで日野さんに言われたのは「大それたことを気軽にやるというのは、エンタメビジネスの基本ですよ」ってことだったの。
うわー! すごい言葉。
実際日野さんもすごくたくさんの借金を抱えたことがあったけど、絶対うまく行くと思っていたから、そんなの全然気にならなかったって。
へえー。
そんなふうに話しながら、少しずつね。結局、不安を打ち消す処方箋なんてないんだよ。毎秒毎秒形を変えてやってくるものだと思うから、その都度、こっちも形を変えて対処しなくちゃいけない。自分の心の中にある、そういう孤独というのか不安というのか闇というのか。それら全部に、一定の対処法があるわけじゃないからね。ある時は山登りをして癒されたり、家庭にいることで癒されたり。時には全く逆で、家庭にいてはいけないって思って、ひとりになりたくなるときもあるし。猛烈に働くことで不安が消えることもあれば、働けば働くほど不安が増すこともあるし。刻々と形を変えていくものだと思っているから、その日その日で不安を見つめながら、それぞれに対処していくって感じじゃないかな。
さっき、社長の仕事についてうかがいましたけど、「リスクを一人で背負う」っていうのも、社長の仕事なんですね。
あはは。そうだよね。オーナー社長だから宿命的にそうだし、何をやるにしても、僕ひとりがすべての責任を負わなくてはいけない。法律上もそうなっているので。……まあ、そうだね。俺のやってる仕事と言えば、責任を背負うってことかな。かっこよく言えばね。
「孤独」であることが飯の種

そういう孤独をわかってほしい、というようなことは、思ったりはしないですか?
思わないかなあ。だって、僕がリスクを背負うまでは、誰かの孤独を100パーセント理解できなかったから。自分自身、「リスクを背負わない」という状態のまま30半ばまで過ごしてきたからね。みんなは「なるほどね、大変だね」とは言ってくれるけど、100パーセント共有できるとは思えないし。
社員に対してもそれは、割り切っている感じ?
その部分ではね。でも、それを会社全体で共有するのもわけわかんないじゃない。会社員と経営者の本分っていうのは違うからさ。僕は、下手したら今持っているもの全部吐き出して、それでも借金を背負うリスクすらあるから、今、他の人よりも多く給料をもらっているんだろうし。それもひとつ、経営者が社員よりも多くお金をもらう理由だと思うけれどね。
じゃあ、「孤独である」ということ自体が……
そう、飯の種っていうことになるよね(笑)。
では、その孤独と引き換えに得られるものって何だと思いますか。もちろん、お給料もそのうちのひとつとは思うんですが、何億円規模の保証人に自分の名前が乗って、すごいリスクをひとりで背負って……そういうことができるのって、何が得られるからなのかなって。
得られるっていうより、自分が作ったアイデアが、そのお金のおかげで世に出ていくって感じかな。そしてその、自分の育てた子供たちが勝つに決まっているっていう、強い意思のもと張るっていう。だからこれからも、自分のアイデア、自分の作ったものに見合う額しか、借りないと思う。
ああ。さっきわたし、「加藤さんはアイデアしか愛していない」って言いましたけど、そのアイデアが世の中に届いて、インパクトや喜びを与えることができると……
そう信じているから。
としか、言いようがないんじゃないかな。
SCRAPに対しての愛を放棄することは未来永劫ない

加藤さんは「経営者を辞めようかな」って思うことってありますか?
ああ、それは結構前から思っていて。
えっ、そうなんですか。
なんならもう今も「経営していない」っていうか。それこそ会社の内部について言えば、精神面では僕が手綱を握っているけれど、制度面では完全に任せてしまっているし。売り上げや利益についても、僕が号令を出してがんがんいうわけでもないし。他の人がうまくやってくれているから、俺自身には「経営手腕を発揮する」っていうモチベーションがそこまでないんだよね。でも、それがつまり、僕が株からなにから全部手放して、SCRAPに対して何の責任も負いたくないってことなのかと言うと、そんなことはない。SCRAPで起きることのすべてに、未来永劫責任を持ちたいなっていう気持ちは誰よりも強く持ってるんだよね。誤解を招く言い方かもしれないけれど、SCRAPは僕のものだという気持ちが強くある。だけど、それはうちの会社で作った作品を全部「俺が作ったんだ」と言い張りたいというわけではない。それは各担当のディレクターが作ったものだし、彼らが褒められたらいい。でも、株式会社SCRAPを褒めるときには僕を褒めてくださいねって思う。「あの作品すごいですね」ってときには作った人が褒められたらいいけど、「SCRAPさんが作る作品はどうして全部おもしろいんですか?」って言われたときには「え? 僕の話ですか?」っていうことかな(笑)。
じゃあ、株式会社SCRAPから加藤さんがいなくなるってことは、今は考えていない。
うん。そうだね。
実務的な意味での僕の重要度は毎日下がっていっているとは思うけれど、ただ、僕がSCRAPに対しての愛を放棄することはないと思ってるよ。

最後にどうしても聞きたいことがあったので、思い切って尋ねた。
「加藤さん、今でも自殺したいって思うことありますか?」
昔加藤さんと一緒にお酒を飲んでいたとき、加藤さんがこんなことを話したことがあったのだ。「自分には幼い頃から自殺願望がある」と。
「だからできるだけおもしろいことをして、自分が自殺してしまわないようにしている」
と、彼は言っていた。
わたしはその言葉をずっと覚えていた。
なぜならそのとき「わたしもそうです」と、自分も言ったからだ。
加藤さんはわたしの質問に「俺、そんなこと言ったっけ?」ときょとんとした顔をする。
そして、
「今は死にたいっていう気持ちは全然ないよ。ひとときでも長く生きていたい」
とはっきり言った。
「子供ができたのがでかいかな、成長を見るっていう大きなモチベーションができたからね」
「それは……大きく変わったことですね」
「そうだね」
平静を装いながらも、正直なところ加藤さんの口からそんな言葉が出るだなんて思ってもみなかったので、とてもびっくりした。
そしてその発言を、ただ子供が生まれて父親になったから丸くなったのだというふうには、わたしにはどうしてもとれなかった。

「うちは今年で終わりだから」
もしかしたら、わたしに自殺願望の話をしてくれた加藤さんは、そう社員に言い続けていた頃の加藤さんなのかもしれないと、ふと思った。
「なるべく早く稼いでとっとと逃げよう」と思いながら、無我夢中で不安と戦い走っていた頃の。
だけど、会社ができてから10年目が見えてきた頃、「これはひょっとしたら続くんじゃないか?」と加藤さんは思い始めた。そして、続けるなら続ける努力をしようと働き方を見直すようになった。
加藤さんはこうも言った。
「『よその会社ではおそらくやっていけないだろうな』って人も働けるような会社にしたい」
わたしはその話を聞いたとき、なんだか加藤さんに“父性”のようなものを感じていた。
それは、これまでの加藤さんからは感じたことのないものだった。
だってわたしは加藤さんを「アイデアしか愛していない人」と思っていたのだ。非人間的なところがあって、こわい人だとすら。
だけど、加藤さんは変わった。ある意味で変わっていないけど、ある意味で変わったのだ。確実に。

加藤さんは、今も芯は「経営者」ではなく「クリエイター」だと思う。
生粋のクリエイターであること、その部分は昔と何も変わっていない。
だけど彼は株式会社SCRAPの経営者として、事業を育て、社員を育て、会社を育ててきた。
それはもしかしたら、「アイデア」だけではなく、その「アイデア」が生まれ育つ土壌すらも、育てる行為ではなかったのだろうか。
加藤さんは、株式会社SCRAPは自分の作品ではないと言った。
だけど、株式会社SCRAPは自分のものなんだと言う。責任も愛も放棄することはないと。
それってなんだか、「アイデア」が育つ家を家長として守っているみたいだと思う。
「9割勝つ」とは言え、何億円もの借用書の保証人欄に自分の名前を書く気分はどんなものだろう。
その不安や恐怖は誰とも共有できないし、軽減されることもない。
だけどじゃあ、その孤独と引き換えに何が得られるんですか?
そんな無神経なわたしの質問に、彼は「自分たちの作ったアイデアが、そのお金のおかげで世に出ていく」ことだと言った。
加藤さんにとっては、アイデアは子供みたいなものなのかもしれない。
彼は、クリエイターとしてアイデアを産み、経営者としてアイデアを守り育ててきた。孤独と引き換えに、「自分の育てた子供たちが勝つに決まっているっていう、強い意思のもと」。

インタビューが終わると加藤さんは、取材場所であった“アジトオブスクラップ京都”のスタッフのみなさんに、「終わったよー」と声を掛けた。
自然と加藤さんのまわりにスタッフさんたちが集まり出して、談笑が始まる。普段は東京にいるから、京都店のみなさんとは顔を合わせる機会も久しぶりなのかもしれない。スタッフさんたちがみんな、加藤さんに話したいことがあってうずうずしているように見えた。
別れ際、
「がんばって書きますね」
お礼とともにわたしがそう言うと、加藤さんはこう返した。
「俺の記事、一行目からおもしろくしてね」
その言葉が昔の加藤さんみたいで、思わず笑ってしまう。
「はい、がんばります」
そう言うわたしは、まるで昔のわたしと変わっていなかった。
やっぱり加藤さんは“先輩”だ、と思う。
孤独と引き換えにアイデアを世に出し続ける“先輩”は、昔と何も変わっていない。
ただ、今の方が昔よりも、ずっと優しい顔をしている。
☆リアル脱出ゲーム https://realdgame.jp/
取材=京都文鳥社
3万件のプロジェクト掲載ノウハウを基に作成した「CAMPFIRE」クラウドファンディングマニュアル