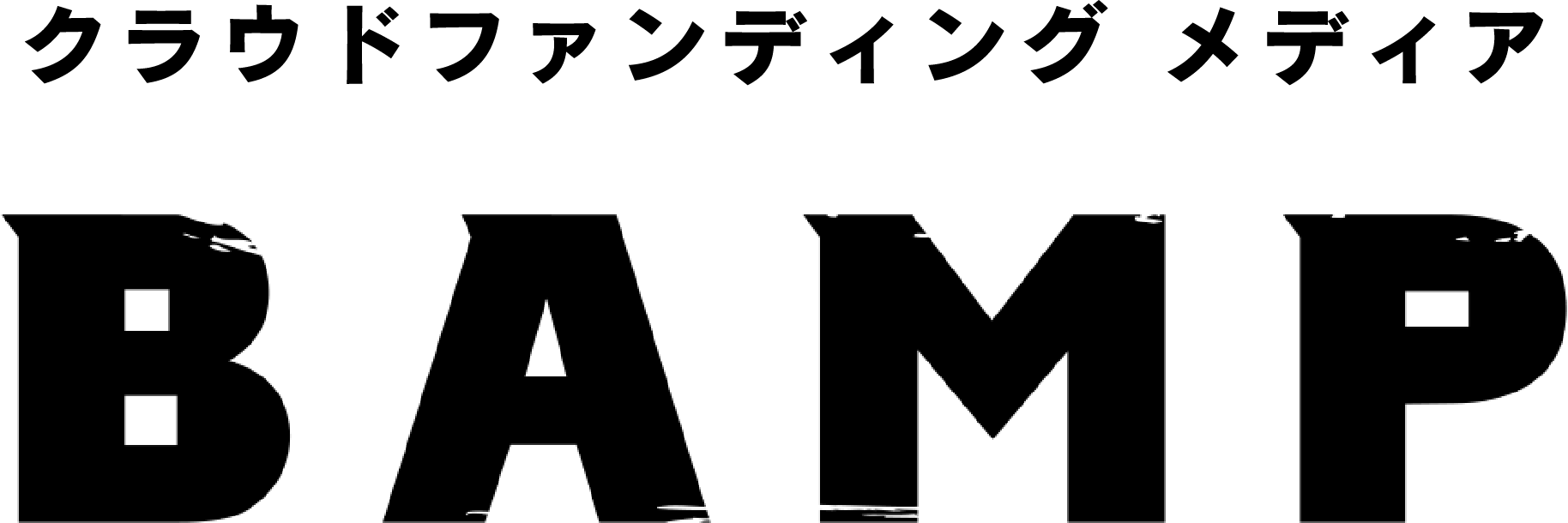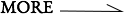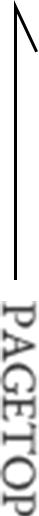たったひとりでリスクをとり、責任をとり、決断をし続ける人々、「経営者」。
彼らを見ているうちにふと気づいたことがある。
それは、わたしの中にも小さな「経営者」がいるということだ。わたしたちはみんな多かれ少なかれ、自分自身の経営者であり、自分の人生という事業を営んでいる。
世の経営者が会社から逃げられないように、わたしたちもまた、自分の人生からは逃げられない。鎧をかぶってこの平坦な戦場を生きぬかないといけない。わたしが経営者に惹かれるのは、きっとそれが拡大化・社会化された存在だからなのだと思う。

『経営者の孤独』という連載を始めてから、半年が過ぎた。
これまでに7名の経営者に取材をしてきたが、この連載を始めるよりもずっと前から、わたしは「経営者」という人種にとても興味があった。
「経営者」という人たちは、文字通り経営をしている人たちだ。
会社を立ち上げ、事業を立ち上げ、社会に対して働きかけをし、なんらかのサービスをする代わりにお金を得る。そしてそのお金で人を雇ったり、事業を大きくしたり、新しい事業を始めたりと、会社は生き物のように変化して、社会の中に息づく。
「経営者」が渦の中心になって、世界に波を立たせていくようだと思う。
その渦や波の大きさに関わらず、まず渦の中心であろうとすることに、わたしは驚きを感じずにはいられない。
どうして彼らは、そんなことができるんだろう。
いや、どうして彼らは、自分にそんなことができると思えるんだろう。
そしてわたしは、どうして自分にはそんなことができると、思えないんだろう。

鷗来堂・柳下恭平「プライベートとパブリックを分けられないことに僕の孤独がある」
「なぜ君はそんなに『経営者』に興味があるの?」
だからそう質問されたとき、とっさに出た答えは、「自分とは違うから」だった。
「どう違うの?」
「世界に対して、なれなれしい感じがする」
「なれなれしい?」
「なれなれしいというと、語弊があるね。世界をこわがっていない感じって言うのかな。世界に手を伸ばして、触って、こねて、自分の好きな形にしている感じがする」
まるで粘土みたいに、とわたしは言う。
「君は世界がこわい?」
重ねて尋ねられ、うなずいた。
「わたしにはそんなこと到底できない。だから彼らに興味があるんだと思うな」

クラシコム・青木耕平「正気でいながら狂うこと。 信用せずに信頼すること」
このあいだ、佐賀県の唐津に取材に行く機会があった。
インタビューのあとに街を観光して、途中で旧高取邸というところを訪れた。
正直に言うと、わたしは歴史的建造物というものにあまり興味を持てたことがない。
きれいだなとか、すごいんだなとかは思うけれど、知識や教養が足りないせいか、恥ずかしながらそれ以上の関心を持てないのだ。
だけど、この旧高取邸だけは違った。
わたしはこれまで、建造物を見てこんなにショックを受けたことはないかもしれない。
それくらい、興味深い場所だった。
この邸宅の主人であった高取伊好(たかとり・これよし:1850〜1927)は、杵島炭鉱などの経営者として知られている。二十歳のときに上京し、慶應義塾にて鉱山学を修得。その後高島炭鉱に入り、35歳で独立してからは、数々の炭鉱を開いて石炭産業を拓いていった人だ。
邸宅の広さは約2300坪。
まるで大きなお寺のようで、これが本当に人の住宅なのかと思うほどに大きい。
女中の人数は多いときで100名ほどいたという。
確かにそうじをするだけで大変そうなほどの邸宅の中を、ガイドさんと一緒にまわった。
邸宅について熟知している彼女は、いっときも飽きさせない話術で案内し、どんな質問にも即座に答えてくれる。
彼女の話を聞けば聞くほど、高取伊好の邸宅には驚かされるばかりだった。
長い廊下には継ぎ目のない一枚板を使用しているとか、暖炉にはイタリア産の大理石が使われているとか、天井が漆喰だったり網代であるとか、いちいちこだわりがあるのはもはや前提。
部屋と部屋をつなぐいくつかの欄間には、動物や植物の絵が彫られており、向こう側から光を透かしてこちら側の壁に絵が浮かび上がるよう設計されているとか、
大隈重信の来訪のために作られたトイレは、日本で初めて有田焼タイルが敷き詰められた場所で、しかもそれが未使用のままであるとか、
邸宅内にはなんと能舞台があり、音響効果も抜群で、そこで観劇はもちろん、高取伊好みずからも能を舞ったであるとか……
ガイドさんはなめらかな口調で驚くべきことを淡々と伝え、高取伊好の邸宅を案内していった。
特にわたしがショックを受けたのは、ある欄間についてだった。
一見、格子柄の組子と思われる欄間をガイドさんは指差し、
「こちらは組子ではなく、実は一枚板を手彫りさせたものなんです」
と言った。
えっ、とわたしは声をあげる。
「手で、彫らせたんですか」
あんまり驚いて、思わずガイドさんに聞き直したくらいだ。
格子柄の欄間をじっと見ると、確かに木を組んだ境目が見えない。
一枚の板を機械のように正確に彫り続けた職人がいたのだと思うと、気が遠くなった。
ガイドさんのあとをついていきながら、わたしは、
「本当のお金持ちって、こういうお金の使い方をするんですね」
とつぶやく。
ガイドさんは遠慮がちに微笑み、「本当ですね」とうなずいた。
「なぜそこまでするんだろう」
ついそう思ってしまうわたしには、到底理解できない、足を踏み入れられない世界が、ここにはあると思った。
圧倒的な知識や教養はもちろん、アイデアやセンス、美意識、そして飽くなき探究心とエネルギー。
いやもうそれ以前に、根本的に何かが自分とはまったく違うんだろうな、と思った。
だけど、その「根本的な何か」ってなんだろう?
そんなことを考えながら邸内を歩く。
窓の外に、緑がかった穏やかな唐津の海が見える。
邸宅を出たあとも、当分のあいだショックが消えなかった。

互助交通・中澤睦雄「だってしょうがない。ほかにハンドルを握る人がいないのだから」
人にはひとりひとり、「世界との付き合い方」というのがあるように思う。
たとえば、世界をどのようなものとしてみなすか。
こわいものとみなすか、親しいものとみなすか。
戦場とみなすか、遊び場とみなすか。硬いものとみなすか、柔らかいものとみなすか。未来永劫続くものとみなすか、自分が死ねば終わる一過性のものとみなすか。
それだけで、「世界との付き合い方」……自分が世界とどういう関係性を築き、どういう立ち位置にその身を置くのかは、ずいぶんと変わってくる。
高取邸を出てしばらく唐津の街を歩きながら、ふと、自分がなぜ世の「経営者」に興味を持っているのかがわかった気がした。
わたしが興味を持っているのは、経営者の「世界との付き合い方」なのだ。
格子柄の欄間をつくるのに、木を組むんじゃなくて、一枚板を手彫りするのはどうか?
そう考えたのは、誰だったんだろう。
高取伊好だったのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
だけど、邸宅の主人である高取伊好が最終的にそのアイデアにGOを出したのは、おそらく間違いないと思う。
手で彫ることによって、その分何倍も時間やお金がかかるだろう。
人員も要るだろうし、手間もかかる。細かな作業の上、失敗だって許されないのだから、職人の感じたプレッシャーだってすごいものだったろう。
だけど彼は、時間、お金、他人……そういった外的要因よりも、自分のアイデアを採った。
わたしにはその事実が、彼自身がこの邸宅の「主」であることを証明しているように思えたのだった。

わざわざ・平田はる香「寂しさはそこにあるもの。哀しみはいつか癒えるもの。孤独は逃れられないもの」
自分が「主」であるということ。
この世界において、自分が「主体」であるということ。
それを自覚していることこそが、わたしが「経営者」に共通していると感じる、もっとも大切な一点なのだと気づいた。
だけどだからと言って、自分が「主」で自分以外が「従」であるというふうに、彼らが世界との関係を上下にとらえているのだと言いたいわけではない。
ただ、自分は「主」たりえるのだと、世界と対等たりえるのだと、自覚しているということ。
手を伸ばせば世界に触れられるし、手を動かせば世界を変えられるのだと、知っているということ。
だからこそ彼らは「経営者」として、世界を波立たせる渦の中心たろうとするのだと、わたしは思っている。
それは自分に自信がある、ということなのかと言うと、単純にイコールではない。
もちろん、「主」として生きることがあまりに自然で気がついたら「経営者」になっていたという人もいるが、
自分がすこやかに生きるためには「主」であることしかできないから「経営者」にならざるを得なかった、という人もいるし、
「経営者」という立場に置かれることで「主」とならざるを得なかった、という人もいる。
そのように、インタビューをしていくうちにいろいろな経営者がいるのだと知った。
そしてその分、孤独にもいろいろな形があるのだと。
いずれにしても、わたしは「主」として世界と対峙している人にとても興味を持っている。
世界に手を伸ばして、触って、こねて、自分の好きな形にしている人。
そして自分自身も、世界によって触られ、こねられ、形を変えられている人。
その姿はまるで、人がこの世で生きるということの縮図のようだと思う。

クラシコム・佐藤友子「誰もが心の中にふたつの金庫を持っている」
「君は世界がこわい?」
そう尋ねられて、わたしはうなずいた。
自分以外のものをひっくるめたものすべてを「世界」と呼ぶなら、わたしは世界がこわい。
昔からそうだった。
時間、お金、他人……そういった外的要因によって、わたしの言動はすぐに影響され、支配された。
「主」ではなく、何かの「従」として生きる自分。
そんな自分に窮屈さと不自由さを感じて、この図式から抜け出したいと思った。
そうしてわたしは、「書くこと」を始めたのだと思う。
わたしが見たもの、聞いたこと、感じたこと……それらを書き付けることによって世界を切り取り、収集し、編集し、つくり直す。
「書くこと」において、わたしはあくまで主体でなくてはならない。
それが、世界に対して「主」として対峙できる、唯一の手段だった。
そのときの衝動を言語化できていたわけではないけれど、この原稿用紙の上ではわたしは自由だと思った。
それと同時に、とてもひとりぼっちだと。
「主」であることは、自由であるということだ。
そして、自由であるためには孤独でなくてはいけない。
だからわたしは聞きたかったんだろう。
「主」である「経営者」たちに。
「あなたの孤独は、どんなものですか?」と。

L&Gグローバルビジネス・龍崎翔子「翔子だったら世界一の経営者になれるよ」
どうして経営者は、世界に波を立たせる渦の中心になることができるのだろう。
そしてわたしは、どうして自分にはそんなことができると、思えないんだろう。
わたしはずっとそう思ってきたけれど、ある意味、わたしは世界に波を立たせる渦の中心にすでに立っているのかもしれない。「書くこと」において、「主」であることによって。
わたしはこの『経営者の孤独』という連載の序文に、
「わたしの中にも小さな『経営者』がいる」
と書いた。「わたしたちはみんな多かれ少なかれ、自分自身の経営者であり、自分の人生という事業を営んでいる」と。
今もそうだと思っている。みんなの中に、小さな経営者はいる。
そしてそれは、みんながみんな、個別の孤独を抱えている、ということでもある。

株式会社ウツワ・ハヤカワ五味「それはあなたの中の『私』であって、本当の『私』じゃない」
これまでのインタビューの中で、
「私、全員孤独だと思うんですよ」
と言った経営者もいたし、逆に、
「もしかしたら本当の意味で『孤独』ではないのかもしれないですね」
と言った経営者もいた。
「孤独は逃れられないもの」
と言った経営者もいたし、
「孤独であっても自由であったりするので、いいのかなって」
と言った経営者もいた。
彼らの話を聞きながら、わたしがやりたいことは孤独を分類することでも、孤独に耐える方法を知ることでもないなと思った。
わたしは、孤独についての話をもっと聞きたい。
それぞれの孤独の源流となる場所に、何があるのかを知りたい。
そのとき何か大切なことがわかるような気がする。
人が「主」として世界と対峙し、交わるということはどういうことか。
人がこの世で生きるということはどういうことか。
だからわたしは、聞き続けるんだと思う。
「あなたにとって、孤独とは何ですか?」

☆この記事が気に入ったら、polcaから支援してみませんか? 集まった金額は、皆さまからの応援の気持ちとしてライターへ還元させていただきます。
『経営者の孤独/インターミッション「この世界に『主』として存在するわたしたち」』の記事を支援する(polca)
【編集部よりお知らせ】
まるで、どこかに隠された井戸を探して砂漠を歩くように、「孤独とはなんだろう」と問い続ける土門蘭の連載は続いてきました。
孤独の源流には何があるのでしょう。今回のインターミッションを読み、孤独を受け入れようとする土門蘭の言葉に触れて、思います。そろそろこの旅も、終わりが近づいているのかもしれませんね。
さて、編集部よりお知らせがあります。
連載を続けてきた本稿ですが、2019年7月にポプラ社より書籍化されることが決まりました!
新たに書籍書き下ろしのインタビューを加えて、さらに深く、さらに鋭くなって皆さんのお手元にお届けしたい。楽しみにしていてください!
同時に、先行予約として、土門さんのファンを増やしたいという思いもあって、クラウドファンディングをすることにしました。プロジェクトをシェアしてくれるだけで、とてもうれしいです。ぜひぜひ、合わせて読んでみてくださいね! よろしくお願いします。
プロジェクトページはこちら!