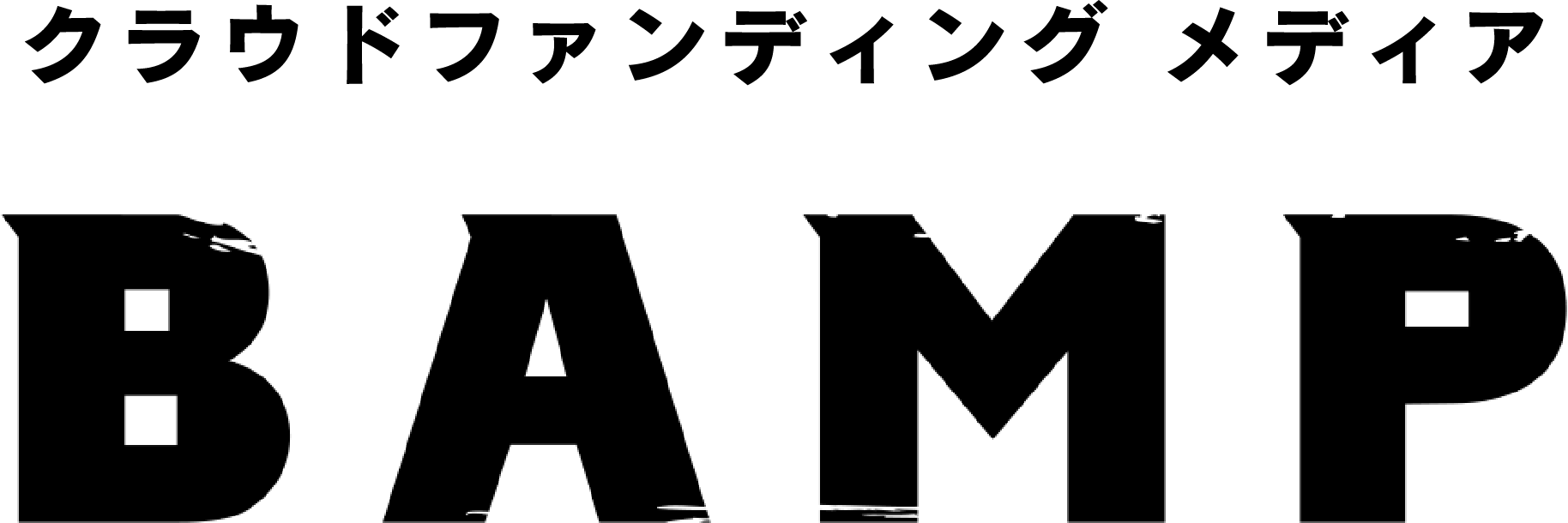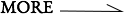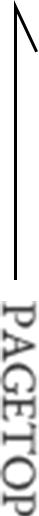約束の場所につくと、赤と青の対照的な色の服を着たふたりの女性が、
雨のなか傘もささずに待っていた。
待たせてしまったバツの悪さからぺこりと頭を下げると、
ふたりは柔らかな表情でそれに応える。
「こんにちは」
相手に安心感を与えながらも、どこか芯のある声。
それは、ふたりがつくりあげた場所『She is』をどこか彷彿とさせた。

『She is』は、カルチャーメディア『CINRA.NET』とそのネットワークを活かしたクリエイティブソリューションで知られる、株式会社CINRAの5つめのメディアとして、2017年の9月にオープンした。
聞けば、会社主導の事業として立ち上がったわけではなく、ふたりの女性社員が自ら構想や事業計画を考え、会社に直談判してつくりあげたという。
ひとりの女性を主語にしたこの場所では、月ごとに“Girlfriends”と呼ばれる女性クリエイターとともに紡ぎだした言葉が、さまざまな特集として提起されるーーたとえば、お金のこと、性のこと、そして生きるということについて。

特集ごとに移り変わり、“Girlfriends”とともにつくりあげるデザインや毎号読者に届くオリジナルのギフトも『She is』の大きな魅力だ。ただそれ以上に本質的なテーマに対して、女性という集合体ではなく、ひとりの女性が率直に意見を述べるという内容が、男性の身からしても心地よく、真夜中にふと開いてしまうことがあった。
コンセプト文にある「ひとりひとりが、無敵かもしれないと思える夜を増やす」の言葉のとおり、広告を一切排し、感覚を同じくする者同士が集うためにつくられた空間は、夜の帳が落ちたあとの孤独感によく馴染んだのだ。
開設から1年という短い期間の中で、変化を迎える『She is』に対する興味の一方で、ひとつ彼女たちにぶつけてみたい質問があった。
それは、「自分らしさ」ということについて。
“She is”は、自分らしく生きる女性を祝福するライフ&カルチャーコミュニティです。
(『She is』about より)
デザインも、コンテンツも、言葉ひとつとっても自由で、とても伸びやかに見える『She is』において、この一言だけが浮いているように感じていたのだ。
SNS時代も10年を経て、「自分らしさ」や「個性」という言葉がもてはやされるようになった一方、その言葉にふりまわされ苦しんでいる人が少なからず存在する。そんなことを百も承知なはずの彼女たちが、なぜこの言葉を使っているのかが気になっていた。
インタビューは、彼女たちが深夜によく歩いているという国道246号沿いを歩きながら始まった。
いつも“午前2時”の話をしているふたり

左から、『She is』編集長・野村由芽(のむら・ゆめ)、事業部長・竹中万季(たけなか・まき)
今回『She is』が1周年ということで、あらためてふたりの関係性についての話から聞かせていただけますか?
そうですね。やっぱり、ふたりじゃないとできないことはたくさんありました。技術的なことはもちろんなんですけど、何より万季ちゃん(竹中)には、物事を一から立ち上げる力があるんです。私は言葉を紡いでコンセプトをつくることはできるけど、物事を前に進める力は万季ちゃんにかなわない。だからこういう場所をつくりたかったとしても、もしひとりならたぶん実現できなかったと思います。
私も本当に、自分だけではここまでたどり着けなかったと思います。由芽さん(野村)の言葉って、私が考えていることをそのまま形にしてくれている気がしていて。肩書きとしては私が事業部長で、由芽さんが編集長なんですけど、基本的にすべてふたりでつくっているし、決まりごともふたりで話し合って詰めています。
事業部長と編集長というのは、それぞれどのような分担なんでしょうか。
事業部長は、事業計画を立てて会社の中のプロジェクトとして進行していくプロデューサー的な役割です。サイトのデザインなど全体のディレクションも万季ちゃんの方が経験的にも豊富だし、得意なので。私はずっと企画・編集を専門的にやってきたので、編集長として特集に添える言葉を書いたり取材をメインで担当しています。
編集・企画・営業・ディレクションのどの分野においても、どちらかしかできないことはないんです。だから、何かを片方に丸投げしてしまうことはないんですけど、お互いの長所や得意な部分を立たせていく役割分担が自然にできているんだと思います。
分担しているというより、お互いに「彼女なら私よりも良くしてくれる」という期待を込めて仕事をお願いしている、という感じでしょうか。

私たちの関係性って、わりと奇跡的なことだなと感じていて。だいたい誰かとペアを組むときって、お互いに自己主張だったり、無用な競争意識を持ってしまうことが多いと思うんです。でも、由芽さんからは、一度もそういうものを感じたことはなくて。それは彼女が仕事をする相手に常にリスペクトを持っているからだし、私が何が得意なのかも知ってくれているからだと思います。
同じプロジェクトをやる中で、衝突してしまうことはないんですか?
4ヶ月に1回くらいは……ありますかね(笑)。どこか噛み合わなくなる、というか。
ふたりの関係で面白いなと思うのは、意見が衝突してしまったときも、なぜ行き違いが起きたかという考えに、すぐに切り替えられることなんですよね。自分の想いや考えをあらためて説明すれば、きちんと応えてくれるという信頼感があるんです。だから常に、次はどうするかを考えられる。
日常的に深い話をしているから、相手の人間性を信じられるんですよ。だからもし「あれ?」と思うことがあっても、その言葉を発した理由や誤解がないか考えます。ものづくりにおいても、どちらかが悪いと追求したり、リスクを回避する方向ではなく、互いによりよいものを求めるほうに意識が向く。そういうところも共通してますね。
『She is』のこと以外でも、けっこうふたりで話してるんですね。こんなふうに帰り道に歩きながら?

ふたりでいるときは、何かしらずっと話してますね。仕事のことだけじゃなくて、個人的な……恋愛やパートナーの話、最近見た作品の話までなんでも。
帰り道もそうです。気分が乗ったら、池尻や三軒茶屋のほうまで歩くこともあって。
歩いたほうが話す時間ができるからね。
夜中ふたりで話してると、込み入った話になっちゃいそうですよね。
でも、わりといつでも込み入ってるかも。いつも“午前2時”くらいの話をしていると思います。
午前2時の話?
「好きって何だろう」とか「生きるってどういうこと」みたいな話です(笑)。答えがないことって話せば話すほど、違う景色みたいなものが見えるじゃないですか。ふたりとも性格的にそれをおもしろいと思えるタイプなんですよ。

ふたりの会話を聞きながら、双子のようだなと感じた。
片方の言葉の足りない箇所を、間髪入れずにもう片方が補っていく。
その心地よいリズムの掛け合いを聞いていると、実はふたりの人格は繋がっていて、
必要に応じてスイッチしているだけなのではないか、と妄想してしまうほどだ。
出自も年齢も異なるふたりが、どれほど同じ時間を過ごし、どれだけ対話を重ねれば、
ここまでお互いを信頼し合えるのだろうか。
「私たちのような人がどこかにいるはず」という祈りから生まれた場所
ある時期に、由芽さんが「フリーになる道もあるかもな……」と漏らしていたんです。そのときに、彼女が辞めちゃったら私ももうCINRAにいる意味がないかもしれないと思って。というのも、実は入社したときから、カルチャーニュースサイトの『CINRA.NET』やクリエイティブの求人メディア『CINRA JOB』とは切り口の違うメディアを立ち上げたいと思っていて。ただ、明確なビジョンがあったわけではなくて、女性のクリエイティブに関連する何か、くらいのもの。それが由芽さんと会話する中で、深まってくる感覚があったんです。
お互いそのとき担当していた仕事にはやりがいを感じていたけれども、「自分たちの場所をつくりたい」という想いは共通していて。
当時、会社の体制や働き方の話をかなり頻繁にしていたんです。どこか追いかけられている感覚もあったし、楽しんでいるはずの仕事が、人生を費やすに値するか確信が持てなかった。改めて考えてみると、やりがいや責任感を持ってやっているつもりだったけれど、本当にやりたいこととのズレがあったのかもしれないです。

ちょうど年齢的に30歳前後で、周りも結婚や子どもの話を始める時期。その中で自分たちは、人生において大切なものとしていまは仕事を選んでいるわけです。でも私たちは、働くことと生きることの間で、常に揺れている。そんな中で、どうしても与えられる仕事だと、目的や表現すべてに共感するのが難しい部分もあって。だとしたら、もっと自分たちのやりたいものに時間や想いを賭けてもいいんじゃないかと。歳を重ね、ある程度経験を積んで、自分たちが大切にするべきものが少しずつ見えてきたこともあると思います。だから、そういう葛藤みたいなものに向き合って、考えることができる場所をつくるべきなんじゃないかと思っていたんです。そんな話をふたりで8ヶ月くらい話して、「She is」の相談を会社に持ちかけました。
なるほど。そこで、ふたりで独立するのではなく、なぜ会社の中でやろうと?
カルチャーが社会を変える! とまではいかないんですけど、個人個人の心を救うことはできる、とは思っていて。その理念を、組織として体現しているCINRAだからこそ、社内で自分たちの『She is』という場所をつくる意味はあるだろうと。初めはもちろん誰からも求められてない状態です。だけど、きっとどこかに私たちと同じ想いを抱えている人がいるはず……という祈りのような気持ちだけで突っ走っていました。怖いけど、自信はあったんです。
ふたりの理想から全体の枠組みを考えていったので、会社への提案時にはまだ構想に近い状態でした。そこから半年間でティザーサイトの立ち上げまで進めることになって。やったことないことばかりでしたし、この期間で具体的に落とし込んでいくのは、本当にたいへんだったよね?

会社でやるにしろ独立するにしろ、仕事としてやる以上、きちんとマネタイズしなければいけません。だけど、どんなに大きなお金をもらえるとしても、バナー広告を載せたり、メディアと思想の合わないクライアントさんとお仕事をするわけにはいかないと思ったんです。なぜなら私たちはそういうメディアのお金の回り方も考え直したくて、『She is』をつくろうと思ったので。メディアとしてのビジネスモデルも一から考える必要がありました。
なるほど。
もちろん、コンテンツをつくってくれる作家さんたちにも、きちんとお金が回っていく仕組みにしたい。それで、自分がいいと思う記事や表現者に対して受け手がお金を支払うことで、作り手に対して愛情や感謝の気持ちを届ける、サブスクリプションモデルを考えました。
お金って、作り手に対して愛情を示す手段のひとつだと思うんですよね。それとメディアをつくる上で、すべてに共通して大切にしたかったことがあります。それは、『She is』は一方的に何かを提示する場所ではなくて、なんだかわからないことをみんなで一緒に考えようよ、という場所にすること。私たち自身、問いかけはするけれど、答えは一つも持ってなかったので。
「答えを持ってない」というのは、「あえて持たないようにしている」ということですか?
たぶん、「それっぽくする」のってすごく簡単だし、そのほうが早いじゃないですか。たとえば『She is』のコンセプトにある「自分らしく生きる」という言葉にしても、いま私たちがいちばんやりたいことを表現できる言葉として、考えて考えてこの言葉を使っています。ただ、「自分らしく生きる」を表面的に捉えることも消費することも、すごく簡単で。だから、コンセプトにしても、先ほどのサブスクリプションモデルにしても、「いったんそうした」というふうに考えています。別の言い方をすれば、もし「She is」っぽさを意識して、自分たちが自分たちの真似をするようになったら、すぐに次に行こう、と。そういう意味では、答えは「あえて持たない」ようにしているのかもしれないですね。
価値観の違うそれぞれの声が、遠い社会と繋がっていく

「次に行く」、というと?
いつ変わってもいいと思っている、ということです。だって「自分らしく」なんて、そんなこと言わなくても済むくらい当たり前になるなら、それが一番いいこと。そうしたらまた、違うかたちを考えればいいだけの話で。
私たちとしては、今やりたいことを表現する言葉として「自分らしく生きる」を使っています。ただ、そこだけ切り出されてしまうと「自分らしい」ことへの強制のようになって、生きづらさを覚える人が増えてしまうことにもつながります。何の問いもなく、一人歩きした「自分らしさ」という言葉だけが気軽に使われてしまうことは怖いことなんです。私たち自身、「自分らしく生きるってどういうことなんだろうね」という話を日常的にしているし、自分たちのプライベートな課題を掘り下げながら、世の中で起きていることを組み合わせて考えていけるようにしたいと思っていて。
何か問題について考えるときに、どこまでが当事者なのか、当事者じゃない人は何も言ってはいけないのか、なんてよく考えるんです。でも、その問題って実はごくごく個人的な問いの重なり合いなんじゃないかなと思っていて。どんなに遠い社会の問題に思えても、自分たちの身の回りに起きていることと重なっている部分が何かしらあるはず。個人的な声がたくさん集まれば、もしかしたら一瞬だけバラバラの価値観も交差するかもしれない。個性だからバラバラでいいというのも違う気がしているし、みんながすべて同じというのもたぶん違う。一人ひとり違うんだけど、少しだけ共通することがあって、それが一瞬重なり合う奇跡みたいことがたまにある。人と人って、そういうことでしか分かり合えないんじゃないかって考えているんですね。
ふたつの首都高速が交差する地点。
赤信号を前にふたりがゆっくりと歩みを緩めていく。
彼女たちの歩幅はずれては重なり、やがてぴたりと止まった。
彼女たちは、人と人とが交差する瞬間を「奇跡」と呼んだ。
時を重ねたからでも、対話を重ねたからでもない。
「異なる価値観の人同士がときどき重なり、尊重し合えることが奇跡」
そう理解しているからこそ、彼女たちは「ふたり」でいられるのだ。

「She is」は、それぞれが別々の価値観を持つことを理解した上で、自由に発言できるコミュニティということですね。新しく4つの取り組みを始めることを発表されましたが、その中のひとつのオンラインコミュニティなども、そういった意図があって?
はい。みんなで同じ考え方を共有しよう、というものではなくて、あくまでそれぞれがバラバラなことを理解した上で、緩やかに集まれるようなコミュニティが理想です。そういう輪をもう少し広げるために新しく立ち上げたのが、この10月から始めたオンラインコミュニティ『She is TALK ROOM』という場所なんです。これまでも『She is』では、文章や作品を公募していたんですけど、ちょっと敷居が高くて、なかなか発信しづらいと思っていた人もいると思うんです。たとえひと言だったとしても、素直に思ったことを発言してほしくて。

たしかに今、ネット上で思ったことを素直に発言するのって、難しくなった気もしていて。
そうだと思います。自由なはずのSNS上でも、周りのことが気になってしまって、消えてしまう言葉がたくさんある。それが『She is』という、ある程度閉じているけれど、その中でさまざまな人とすれ違うことができる場所でなら、今まで押し殺していた言葉が発せるようになるかもしれない。そこで、まったく異なる価値観のふたりが少しだけ重なりあう奇跡みたいなものを、もっと増やせるんじゃないかなと期待しているんです。
安心して自由に発言できる場をつくることによって、それぞれにとっての「奇跡のような瞬間」を起こせるかもしれない、と。
私自身、中学から高校時代にインターネットに救われた経験があって。学校自体は楽しかったんですけど、周りの人と少しずれているような孤独感も抱えていたんですね。自分の好きなものの話をしたとしてもきっとわかってもらえない、みたいな感覚で。

でも、インターネットの海の中では、自分しかわからないと思ってたものを好きと言っている人を見つけることができたり、あるいは私がまったく知らなかった魅力的な世界を見つけることができた。年齢も性別も異なる顔も知らないような人たちに、初めて自分の考えていることを話すことができたんです。だから『She is』がそういう場所になればいいと思って。
私は銭湯や旅に行くのが好きで。そういう常識や時間感覚の異なる場所に自分の身を置いたときに、改めて自分の輪郭が見えてくる気がするんです。例えば海外に行くと「あれ、自分はなんの常識の中で生きていたんだっけ?」と今まで縛られていたものに気づくじゃないですか。だから、たとえ学校のクラスにうまく馴染めなかったとしても、その人の個性は世界中のどこかにはハマるはず。いま自分の身の回りにある常識や社会だけが絶対的な正解なんかじゃないんです。自分と重なる人が確かに世界には存在することを知ることができれば、生きる意味を見いだすことができると思うんです。それは旅や人との出会いだけではなく、本や映画などのカルチャーに触れたときにも起こります。いま、自分のいる場所から離れたところに視点を置くことで見えてくるものがあると思うんです。
肩書や所属という枠組みにはある種の安心があるけれど、枠組みに縛り付けられている自分には、見えないこともある。“女性”ということに関してもそうで、多くの人がほぼ無意識のうちに「女の人があるべき姿」という観念を持っているし、時としてそれを求められることもある。「あるべき女性」のままでいるほうが楽なときもあるかもしれないけれど、その枠組み以外の選択肢があることを知っていたほうが、違和感があったときに選ぶことができるんじゃないかな。だから、さっき由芽さんの言った「答えはあえて持たない」ではないけど、できるだけ「絶対的な何かへの崇拝」や「枠組みへの盲信」みたいなものを疑っていかないといけないなと思ってるんです。
言葉を疑うべきということですか?
言葉の力は信じているんです。ただそれは何かを定義したり固定するものではないと思っていて。言葉って意味もメッセージ性も、時代や発信した人、受けとる人によって、常に変わっていく流動的なもの。だから、言葉って定義づけるためのものではなくて、きっかけなんじゃないかって。感情や思考を喚起させて、考えたり問いかけられるためのもの。何かを流動させるためのものが言葉。

「言葉は何かを縛りつけるためのものではくて、きっかけを与えるもの」
「自分らしさ」という言葉に違和感を覚え、縛られていた自分には、この言葉自体がもっとも大きな問いかけのように思えた。
揺れ動く人にこそ、絶対的な肯定をしてあげたい

…なんだか、ふたりはずっと読者に「そのままでいいよ」と言っているような気がして。
問いかける気持ちもあるんですけど、本当は何かに迷っていたり、不安だったりするって状況にいる限り、あなたは大丈夫なんだよって言いたい気持ちもあって。つまり、何かに迷ったり、揺れ動いたりしてるってことは、すでに自分に対して問いを立てている、と思うんですよね。不安で苦しいこともあるかもしれないけど、その時点で次に行ける準備はできているはずだから。『She is』には、「祈り」や「祝福する」みたいな言葉がよく出てくるんですけど、それは問い続けたり思考し続けることに対して、絶対的な肯定をしたいし、寄り添いたい、という意味があって。
ふたりで仕事するときも肯定的であることを意識しているんですけど、『She is』という場所自体、常に光のほうに向けていたいと思っているんですよね。
光のほう?

たとえば同じテーマを考えるときでも、皮肉っぽく向き合うと息苦しくなってしまうじゃないですか。だけど自分たちは、悩み続けながらもいかに自分たちなりに明るい方向に向かっていけるか、という姿勢を大切にしたい。ただでさえ何かを考え続けることはとても苦しいのに、ずっとネガティブな気持ちで向き合い続けたら、どこかで考えることを諦めてしまう気がするんです。もちろんときにはネガティブな問いかけをしないといけないこともあるかもしれない。だけど、それでも考え続けるために、『She is』は閉じていく方向ではなくて、できるかぎり明るく開いているほうに行きたいんです。
以前、小説家の西加奈子さんにインタビューしたときに、彼女はこんなことを話してくれました。
今、社会が少しずつだけど多様性という方向に向かっているのは、これまで当然のように取りこぼされてきた人たちが、自分たちの場所をつくっているからでもありますよね。それは、She isの成り立ちもきっとそうなんじゃないですか?
でもだからこそ、私が全ての読者を網羅しようと思わなくてもいいし、She isもそれをしようとしなくてよくて。私たちが取りこぼした人は、別の誰かが拾ってくれて、そうやって未来ができていく。
西さんがおっしゃっているように、『She is』は当事者としての「she」から始めたけれど、性別を問わず枠組みに生きづらさを感じているあらゆる人とともに歩んでゆきたい、と思ってます。

だけどもちろん、ここには私は入れないと思う人もいるでしょうし、あるいは枠からこぼれてしまう人もいる。だけど、その人たちもまた新しい何かをつくればいいと思うし、それを見て私たちもいいねと言えればいい。そういうことの連続でしかないというか。
尊重し合うことはできるし、また交わる瞬間はくる、というか。
はい。たぶん何かをつくったり発信することで、どれだけ多くの人が喜んでくれたとしても、一方で傷ついている人は絶対にいるんです。そして、自分自身も必ず傷つく。それはもう、何を書いても何を言ってもそうで。ただ、折り合いが合わない瞬間は互いにあると思うけど、気持ちを交わしてない状態ですれ違うということはしたくない。できるなら会って話そう、そう思っています。

取材の後、夜の街をひとり歩いて帰ることにした。
時刻はちょうど午前2時。彼女たちが「声明文」と呼んだ、野村さんの文章を改めて読み返す。
誰から求められたわけでもなくつくる場所のほんとうのはじまりは、とても楽しみでとても怖い。いいも悪いもあるでしょうし、死にたくなっては、めちゃくちゃに生きたくもなるでしょう。女と男がいる世界の、その間にある無数のなめらかな選択肢を選べるということが、私たちを生かす。そんなハッピーエンドの未来から逆算して、この場所をはじめます。今日も春のような秋で、朝には蝉も鳴いていたのでした、すべては溶け合って。
あたりは静まり返り、灯りもまばらだ。
空を見上げると、あるはずの月も雲に隠れている。
住宅街を縫うように歩いていると、
自分が本当にここに存在しているのかと不安になる。
ふと「僕は、ここにいるぞ」なんて言葉が口をつく。
自分の耳にだけ届いた、小さな声。
この声も、いつか誰かのもとに届くのだろうか。
もうすぐこの街にも光が差し込む。
☆この記事が気に入ったら、polcaから支援してみませんか? 集まった金額は、皆さまからの応援の気持ちとしてライターへ還元させていただきます。
『「揺れ動くあなたなら大丈夫」She is ──“自分らしさ”が交わる場所』の記事を支援する(polca)