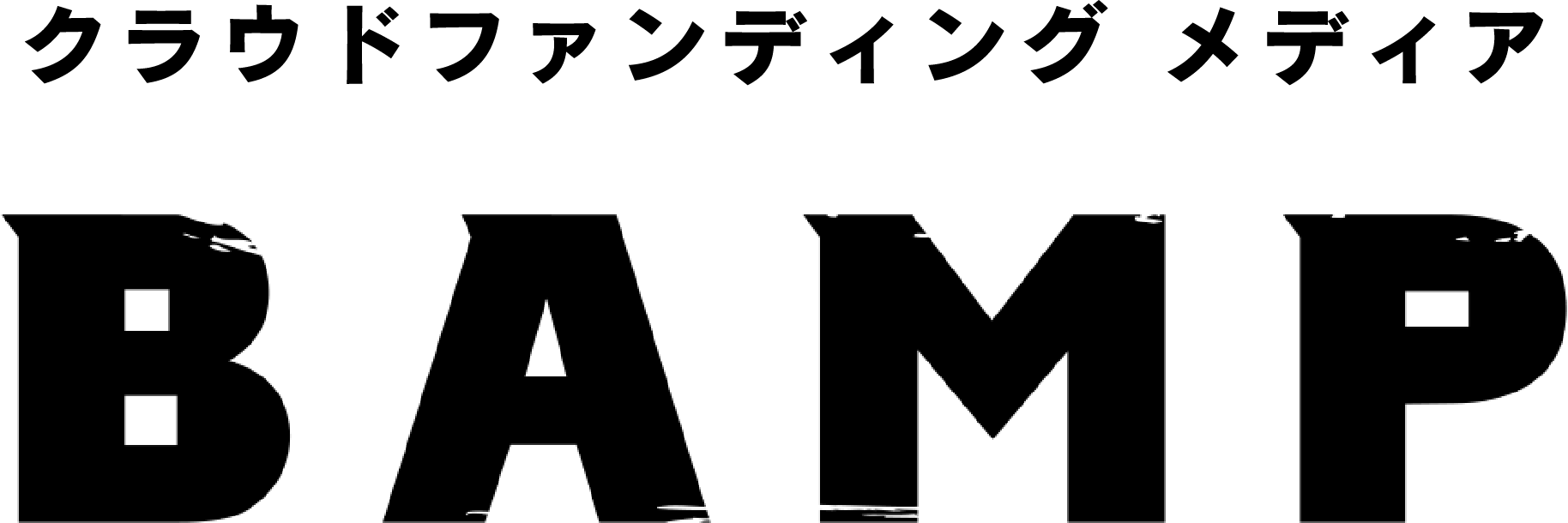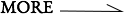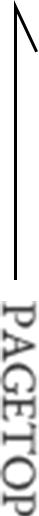本を読む人が減っていると言われる時代。必要な本はAmazonでぽちっと買うというならまだしも、そもそも本を読まない人が増えているなか、本との出会いの入口でもある末端の書店が苦境に立たされているとはよく聞く話である。
しかし、そんな状況を意に介さず、現場で本を売りまくる女性が三省堂書店のカリスマ書店員こと、新井見枝香(あらい・みえか)さんだ。

約10年前に三省堂書店にアルバイト入社。その後めきめきと頭角を表した新井さんは現在、正社員として神保町本店に勤務し、文芸書を担当している。
彼女の取り組みが注目を集めるきっかけのひとつになったのは、2014年に文芸作品を独自に選考し、芥川賞・直木賞と同日発表する「新井賞」を設立したこと。彼女が選んだ本は芥川賞・直木賞受賞作よりも売れるといわれ、業界内はもとより、作家からも厚い信頼が寄せられている。

カリスマ書店員としてテレビやラジオにも多数出演する新井さん。業界内外で注目を集める存在だが、一方では作家としての顔を持ち、昨年12月には初のエッセイ本『探してるものはそう遠くないのかもしれない』を出版した。文庫解説や帯コメントの依頼もこなし、執筆活動も精力的に行っている。
いち組織人としての枠組みを飛び越え、自分の顔と名前を前面に出し、自由に仕事をしているようにも見える新井さん。なぜ、彼女は「本」と「文章」というツールを使って、業界内外に独自の存在感を発揮し続けることができるのだろう。書店員であり作家でもある新井さんの人生哲学に迫った。
プロフィール
新井見枝香(あらい・みえか)
その棚は信頼できるか

新井さん、今日はよろしくお願いします。まず、新井さんの書店員としての日常を教えてください。
文庫担当なので、新刊が入ってくればそれを棚に出したり、補充をしたり、売れない本を下げたりということを一日中やっています。棚に置ける本の量は決まっているので、何かの本を出しては何かの本を下げるといった取捨選択を常にしていますね。
棚づくりにセオリーのようなものはあるんですか?
例えば、平台でも「エンド」という端っこにある本が売れやすいんです。さらに一番売りたい本は真ん中よりも右端に置くと人は手に取りやすいというような、一応のセオリーはあります。
ただ、何をどう見せるかということに正解があるわけではないので、説明がすごく難しくて……。
感覚的にやっているようなところもあるんですか?
あります。常に棚の中身を変えて、トライアンドエラーを繰り返していくうち、だんだんいろんなことに気付きはじめました。棚は生き物みたいなものなので、やっぱり手をかけ続けないと分かり合えないようなところもあるんでしょう。
おもしろいですね。新井さんの棚にあって、ほかの棚にはないものが何かが気になります。
それでいうと、私はこの棚は信頼できるなと思ってもらえたらうれしいと考えていますね。お客さんは買うことが楽しくて来ているので、やっぱり信頼できない棚から本を買いたくないと思いますし。

信頼。それはどうやったら表現されるんですか?
例えばひとつの棚のなかで、売れ筋ランキングの1〜100位を単純に詰めてもだめなんです。そうではなくて、ある本を打ち出したいとしたら、それに紐付いていると考えられる本も並べる。これを置くならこれもないと変だよなっていうところを、ちゃんと押さえているのが大事だったりするんです。
なるほど。「わかってる感」というか。
はい。だから私はサブ的に置く本には必ず意味を持たせます。それが一年に一冊くらいしか売れない本であってもいいんです。
ただ、それは本好きに向けたもの。実はもう私が担当している棚に関しては、そういうことはある程度できたと思っています。だから本好きはもちろん、それほどでもないという人にも受け入れてもらうための取り組みを、これからも考えていきたいんですよね。
「言いたい」を受け止める
それでいうと、「新井賞」や「新井ナイト」はユニークな取り組みだと思いました。どちらにも熱心なファンが付いていると聞きますし、読書人を増やすための活動としては、意義深いものがあるなあと。
書店員の営業としてはとても地味なことをしている感覚はあるのですが、私もやる意味はあると思っていますね。
というのも、まず「新井賞」ですけど、これを始めてから私のところにお客さんが直接、本の感想を言いに来てくれるようになったんです。おもしろかったという人もいれば、おもしろくなかったという人もいるんですが、なんでそう思ったのかをみなさん話しに来てくれて。
ああ、本って感想を誰かと分かち合いたくなりますもんね。

そうなんですよね。それでいうと、前の店舗にいたときは、お客さんとフロアで1時間半くらい話し込んだこともありました。2回目の「新井賞」を発表したときですね。早見和真さんの『イノセント・デイズ』(新潮社)のラストがもやっとしていたことについて延々と……。
そのお客さんの熱量もすごいですが、応対する新井さんもすごい。
私もその本を選んだ手前、納得してもらうまで話をしたかった気持ちもあるんです。でもそうやってたくさん話したことで、そのお客さんは私がどの店舗に異動しても来てくれるようになったんですよ。これからも『新井賞』は全部買うと言ってくれて。
おおー。それは貴重な存在だなあ。
本を読む人が減っている時代でもありますし、絶対読むと言ってくれる人をなくしちゃいけないなあとは思いますね。
では「新井ナイト」でのお客さんの反応はどうですか?
これもみんなの「言いたい」を受け止めているようなところはありますね。
「新井ナイト」は人数少なめのアットホームなイベントで、私が作家さんと打ち合わせなしにあれこれと話をするんです。これまでに道尾秀介さん、湊かなえさん、ジェーン・スーさんなど、たくさんのゲストをお招きしてます。
昨日の新井ナイトは道尾秀介さんのトークが冴え渡りました。『サーモン・キャッチャー』はもちろん、『光』や『鏡の花』の、ここでしか聞けない裏話など、貴重な機会だったと思います。来場者の皆様、ありがとうございました。 pic.twitter.com/QyGThWNgsq
— 鈴木一人 (@dorobohitori) 2016年12月7日
このイベント自体を私自身が楽しんでいるのですが、みんなが話しやすい空気をつくりたいと思っているのもあって、トークの途中からお客さんたちの口が次第にもごもごしてくるのが分かるんですよね(笑)。
もごもごというのは、何か自分もひとこと言わせて欲しいというような?
はい。だからトーク後のサイン会がとても盛り上がるんです。お客さんと作家さんの距離も縮まりますし、みんながその作家さんに親しみを感じて、応援したいという気持ちが強くなっていくとしたら、すごくいいことだなあと思っているんです。
ただ、イベントの準備は毎回結構大変で。なんでこんなのやるって言っちゃったんだろう……家で本読んでたいよ……なんて思うんですが、やりきるとやってよかったなあって毎回思うから不思議ですよね。
「日用品」としての本を売ること

新井さんはそうしたさまざまな取り組みを通じて、本への入口をつくっているんですね。それでいうと、本屋さんというのはふらっと足を運んだときに、本との偶然の出会いを与えてくれる場所であると考える人もいます。書店員として、そういう出会いを意図して演出することはあるんですか?
私はしないですね。だって、本そのものはそれほどのものじゃないですから。本ってもっと日用品なんですよ。それでいいはずなのに、最近は「ここに来なかったらこの本に出会えなかった」というような美談が世の中にあふれている気がしていて……。
まあ、わかります(笑)。
本屋さんにすてきな出会いを求めるのは自由ですし、そういう出会いを生み出すセレクトの店があってもいいとは思います。でも、うちみたいな大型書店はそれだけじゃやっていけないんですよ。
本はもっと気楽にわさわさっと選んで、レジにどん。それでいいし、そういうものなんじゃないですかね。
最近はみんな本を読まないこともあって、本屋さんにちょっとファンタジーを持ちすぎているところがあるのかもしれませんね。
でも、本はやっぱり日用品なんですよ。私はレジに立つのが好きなんですけど、お客さんが本を買う様子を見てわかるのは、小説なんて売上のほんの一部であるということ。多くの人が買う本ってテレビ雑誌とか、NHKテキストとか、何かの試験の教本とか、赤本とか……必要に駆られて買っているんだろうなあというものばかりで。
そうなんですね。とても実用的だなあ。
そういうものが揃っているのが本屋さんの第一条件だと私は思っています。ですが、そうじゃないところにばかりスポットが当たっているなあ……と感じるのが最近ですよね。
逆に、そんなファンタジーの部分が目立ちすぎると、本なんて分からないし……という人が引いちゃうんじゃないかと。そこはうちみたいな本屋さんがちゃんと受け皿になっていきたいとは思っています。
書店員は観察している

ちなみに新井さんにとって、レジってどういう仕事なんですか? 棚をつくるのとはまた違う気付きがあるのかなあと。
私の場合は、ちゃんと売っている実感が欲しいと思っているんですよね。お客さんに直接向き合って「ありがとうございました」とやらずに、棚だけつくって本が売れたとしても、ちゃんと商売している実感が湧かないですから。
あと、お客さんを見るのが好きなんです。買う本でその人のことがわかっちゃうというか。あ、モテたいんだなとか……不倫してるのね……とか、でもこういう試験も受けるのか……みたいな(笑)。人が棚からどんな本を手に取るのかも、実は超見てるんですよ。
書店員さんにそんなに見られているとは思いませんでした……(笑)。
人によるとは思いますけど、私の場合はそうですね。この前トークイベントを一緒にやった「神楽坂モノガタリ」という本屋の久禮亮太(くれ・りょうた)さんも同じことを言っていました。
本の間に挟まっている細長い短冊みたいな伝票を「スリップ」というんですが、久禮さんは売り上げた本のスリップを見ながら「ああ、これとこれを一緒に買ったということは……」と、お客さんの生活スタイルを想像するらしいんです。

スリップ。市販されている本のなかに挟まれる二つ折りの伝票のこと
それはまた、おもしろい遊びですね(笑)。
久禮さんは『スリップの技法』(苦楽堂)という本のなかでそのことを書いているんですが、私もその楽しさはすごくわかるなあと。だって、本はそれを求める人の思考や欲望が全部見えてくるような気がするじゃないですか。そこがおもしろいんですよね。
なるほど。そういう観察力が、書店員としてお客さんのニーズを掴むことにもつながっているのかもしれないですね。
まあ……観察というと偉そうなんですが、そういうことをおもしろがれる性格ではありますね。
なので、私は本が好きで、本について話したくてしょうがないんだろうなあ……という人を当てるのも割とうまいんです。話さなくても、なんとなくの雰囲気でわかっちゃうんですよ。
人は嫌い。でもお客さんは好き
ここまで話を聞いてきて思うんですが、なんか新井さんってとても独特な雰囲気ですね。これはそもそもの話ですが、なんで本屋さんをやってるんですか?
たまたまです。バイトで入って、そのままおもしろいからずっとやっているんです。文章を書くのも昔から好きで、それもおもしろいからずっと。それでどうにかなりたいとかもなくて、ただ書いて遊んでるような感じですね。あー楽しいって。
新井の狂い咲き #探してるものはそう遠くはないのかもしれない #三省堂書店神保町本店 pic.twitter.com/UEdyzITJXB
— 新井見枝香「探してるものはそう遠くはないのかもしれない」 (@honya_arai) 2018年3月19日
世間から注目されている存在なのに、とても肩の力が抜けていますよね。緊張はしないんですか?
しないですね。20代の終わりくらいに一回心が死んで、生まれ変わったようなところがあります(笑)。そこからはイベントなどで人前に出てもまったく緊張しなくなって。
へええ。すごいなあ。
そうなったのは、たぶん私が人にあまり興味がないからですね。むしろ、人嫌いといった方がいいのかもしれない。基本的にそうだから、人には何も期待していないし、自分にも何も期待していないんです。そもそも、私は自分のことが好きじゃないんですよ。
好きじゃないんですか。
はい。好きじゃないから、自分をずっと客観視してきたところがあるのかもしれません。だから私にとってはあらゆることが、他人事なんです。緊張しない理由があるとしたら、それかもしれないですね。
でも、新井さんがこれまでやってきたことって、本を通じて人と向き合うことでもありますよね。人嫌いというのがどうも腑に落ちなくて。
私は自分が嫌いです。自分は気持ちも翻すし、信用できない存在だから。でも、人はみんなたいして変わらないじゃないですか。私と同じようにほかの人もそうなんだろうと思うから、私は自分と同じ生物である人が嫌いなんです。人を嫌いになるかどうかは自分が基準ですから。
なるほど。では今、こうして本を通じて人と向き合っているのは?
本を通じて何かを考えている人を見るのがおもしろいからです。書店員の仕事はそれができるから楽しいんです。本は好きだし、観察対象としてのお客さんも好きだけど、特別に人が好きだからこの仕事をやっているわけではないんですよね。

なんか、新井さんがカリスマ書店員である理由が見えてきた気がするなあ……。
大したものなんて何もないですよ。
ただ、私は人が嫌いとはいっても、小説に出てくる人は好きなんですよね。それはたとえ凶悪犯でも嫌いじゃない。小説のなかに出てくる人には、リアルな人以上に興味を持って向き合えるようなところがあるんです。
それって、リアルには諦めた何かを本のなかに見出しているようなところもあるんですか?
どうなんでしょう。ただ、少なくともリアルには見切りをつけているし、いろいろ諦めているようなところはありますね。
漫画家の西原理恵子さんが「幸せのハードルは低い方がいい」と言ってましたが、確かになって思うんですよ。幸せのハードルは低ければ低いほど、些細なことにも幸せを感じられますからね。
ただ、私自身のことを言えば、エッセイにも書いたんですが、生きるのに向いてない。会社にも向いてないし、結婚にも向いてないし、大人にも向いてない。そういう人間です。
そういうところがとても魅力的ですね(笑)。新井さんは今、幸せですか?
今はやりたいことがやれているから幸せです。書店員としての仕事も、作家としての活動もどちらもおもしろいですから。ただ、私はそれらをやり続けて何か成し遂げたいと思っているわけではないんです。
今は自分の仕事が楽しいし、みんなに求めてもらえるからできることをやっています。でも、みんながその仕事を必要としなくなったり、私自身がおもしろいと思えなくなったら、そのときは全部捨てて逃げ出すんだと思います。
執着はしないと。
はい。執着したり、あるいは何かを守らないといけないと思った瞬間から、生きることが苦しくなるのはわかっているので。
永久に続いていくものなんて、この世には何もない。そのくらいには人生を諦めてから始まるものも、きっとあると思うんです。