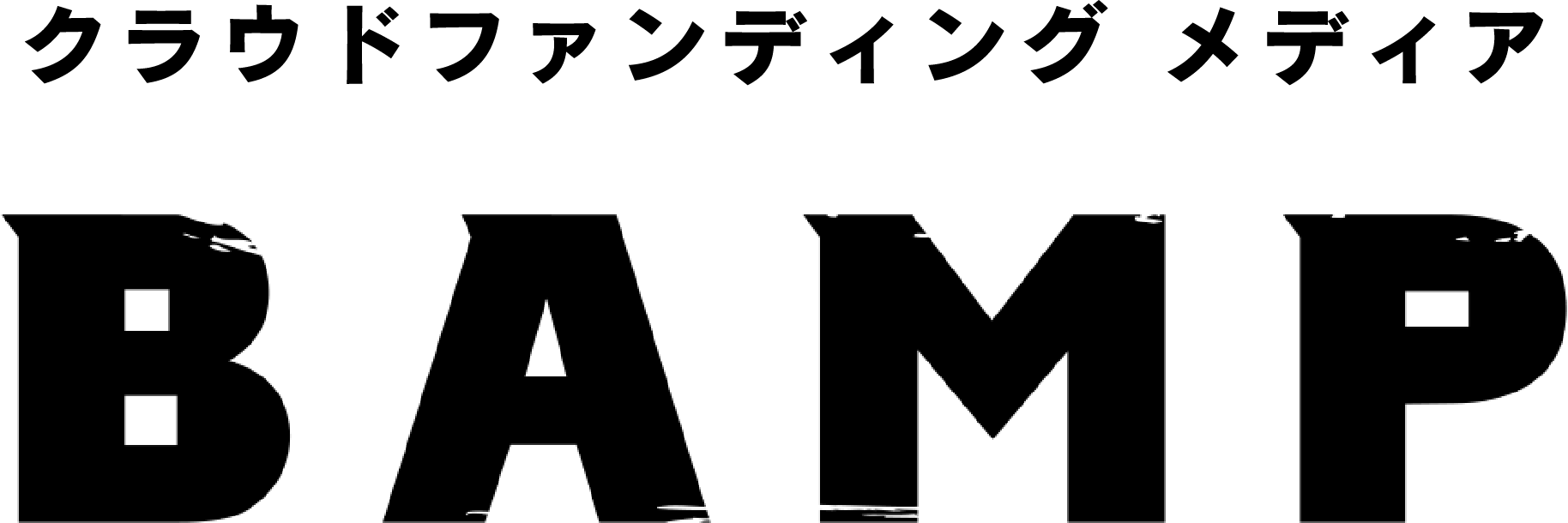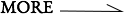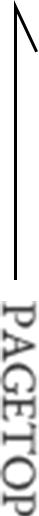引きこもり・不登校など社会的に居場所を見つけられない子どもたちのための学習塾「キズキ共育塾」を運営するキズキグループ代表の安田祐輔氏。最近出版された自伝『暗闇でも走る』にはどこにも居場所がなかった彼自身の生い立ちについても記されている。
自伝を読み、私は彼に「生まれ育った街を一緒に歩かないか」と持ちかけた。横浜、藤沢、家庭の崩壊、学校での孤独。これは『暗闇でも走る』前半部分のアナザーストーリー。

「ごめんね、お母さんはもう家に帰りたくないの」
1990年代前半。横浜市金沢区にあるファミリーレストランの一席。時間帯は確か夜だった。当時小学校高学年だった少年は、突然家に帰ってこなくなった母親と久々に再会した。彼はテーブルの向かいに座っていた母親にこう聞いたという。
「お母さん、なんで家に帰ってきてくれないの?」

実のところ、少年は母親が答える前からその理由を知っていた。
度重なる父親の浮気、不倫。3歳になる頃からの記憶がちゃんと残っている。父親が朝方に帰ってくると、母親との喧嘩が始まる。その絶望的な口論を、何日も、何年も、ずっと聞いてきた。
「祐輔、ごめんね、お母さんはもう家に帰りたくないの」
そう、母親は答えた。
その後しばらくして、母親は再び家に帰ってくるようになったという。ただし、その帰りは夜中の12時を過ぎることが多く、少年は母親が父親以外の別の男のところに行っていることを知っていた。
「お母さん、先に寝ます。おやすみなさい」
少年は毎晩こんなメモ用紙をテーブルの上に残していたという。そして、真っ暗な部屋で一人、布団に入って目を閉じた。

少年の名は安田祐輔。日本がバブル絶頂期へと向かう1983年に生まれた。
生来、発達障害を抱えており、家族関係にも恵まれたとは言えない。学校にも仕事にもなかなかハマらず、家に引きこもった時期もあった。うつ病も患い、これまで幾度もの回り道を繰り返してきた。
そんな安田も34歳になり、いまや150名ほどのスタッフを率いる経営者となった。彼が経営するのは引きこもりや不登校の若者向けに特化した学習塾「キズキ共育塾」などを運営する企業とNPOである。
安田の困難な生い立ちを知って、私は彼が育った場所を実際に見てみたいと思った。そのことを安田に伝えると、彼は私のいくぶん下世話な興味を受け入れ、とある平日の朝に京急線の金沢文庫駅を待ち合わせ場所に指定した。
その日は、安田自身にとっても、久しぶりに子ども時代の「暗闇の記憶」を振り返る1日になった。

真っ白なニュータウンで起きた家庭崩壊
そのニュータウンは駅から離れたところにある。1980年代後半、小高い坂の上に造成された。2階建ての真っ白なフラットが5棟。そこに別々の土地から移り住んできた数十の家族、数百の人々が隣り合って入居した。
どの家庭も、大体は30歳前後の両親に子どもが1人か2人という構成。伝統的な地縁や血縁とは無縁の、真っ白で、新しい街。そこに、見た目や形式が似通った家族たちが寄り集まって暮らしていた。

一つ一つの部屋の間取りは3LDKや4LDKのファミリータイプで、敷地内には小さな公園もあった。装飾の少ない、モダンな、砂場と鉄棒だけの公園。バブル真っ盛りの日本で数多く作られた「憧れの街」の一つ。もちろん、そのニュータウンも安田と同じだけ歳を重ねていた。
当時の安田の家を振り返ると、経済的には「中の上」「アッパーミドル」だったという。父は大手企業に勤める高給取り、母はかつてアナウンサーを勤めたような美しい女性だった。
駅から遠いので、母親が毎日、父親を駅まで送り迎えする生活。車は常に外車だったが、その後暮らしぶりがどんなに苦しくなっても車を手放すことは難しかった。階級的なアイデンティティの一部となっていたのかもしれない。

周りの子どもたちと同じように、安田少年はピアノや水泳を習っていた。ちなみに彼は絶対音感の持ち主で「サイレンやクラクションなど日常の多くの音が音階で聞こえる」。
両親に「ピアニストになりたい」と夢を語ると、母親は応援してくれたものの、父親は「大人になったらどうせ変わるだろ、そんなもので食えるわけもない」と答えた。

安田の家庭の問題は、いわゆる経済的な意味での「貧困」ではなかった。しかし、家庭自体は確実に壊れてしまっていた。大きな理由が父親の不倫による夫婦の不仲。そして母親も意趣返しをするように不倫をし、家に帰ってこなくなった。加えて、父親は安田をよく殴った。
実は、安田家は大して広くもないニュータウンの中で一度引っ越しをしている。同じニュータウンの中で同じような分譲住宅を一度買い直しているということだ。
「最初は1階の普通の部屋に住んでいたんですが、途中でメゾネット型の部屋に引っ越しているんですよね。そっちの方が少しだけ豪華で。メゾネットだから。多分、父親としては壊れてしまった結婚生活をやり直したいという気持ちがあったんじゃないかな」

結果として、その思いが成就することはなかった。互いの不倫の結果、安田が中学生の頃に両親は離婚している。
「強くなろうと思った」小学校時代
ニュータウンのすぐ近くに、安田が毎日通っていた小学校がある。折角だから行ってみようと促した。校門脇のインターホンを押して事情を説明すると、学校の中に入る許可をいただくことができた。
校庭に足を踏み入れる。すると、安田の脳裏にそれまで忘れていた記憶が蘇ってきた。運動会にまつわるいくつかのほろ苦い記憶。

小学校低学年の頃、運動会本番の二日前だった。何かの拍子に安田は父親から猛烈に殴られたという。彼は、腫れた顔のまま運動会に参加した。
4年生か5年生の運動会には、母親がいない中で参加した記憶がある。安田にはほかの子達の楽しそうな様子が猛烈に羨ましく感じられた。同級生が家族でブルーシートを広げて弁当を食べているなかで、安田は一人、料理に不慣れな父親が用意したサンドイッチを食べていた。
「子どもの頃から今まで“他人と比較して同じものが自分にはない”というつらさや剥奪感とずっと向き合ってきました。子どもの頃の運動会はそんな思いの原点にある体験だったのかもしれない。今まで忘れていたけれど、ここに来て思い出すことができた気がします」

果たして、小学校での安田はどんな子どもだったのだろうか。
「発達障害の特性から運動神経が悪かったり図工が苦手だったり、とにかく鈍臭かったのでいじめられることもありました。それにしても、なんで逆上がりってできないといけないんですかね…」
「ただ、自分もいじめられっぱなしというわけではなくて。いじめられると、やり返してしまうようなところもありました。親のことやいじめのこともあって“強くならなければ”という気持ちを持つようになったのを覚えています」
両親のことを「こんな人間はまともじゃない」と思っていた安田は、大人嫌いで不合理と感じたことには理屈っぽく言い返していく、そんな子どもに育っていた。
「学校で“漫画本は基本NG、ただし歴史ものなら持ち込んでもいい”という変なルールがあったんですよ。OKだったのは『三国志』とかですね。でも、自分は『週刊少年ジャンプ』を持っていって、他の生徒から“それはダメだろう”と言われたんです。その時に、“『三国志』を読むことが歴史の勉強に繋がっているというのなら、この質問に答えてみろ”とやり返したのを覚えています。常にファイティングポーズを取っていた、そんな感じでしたね」

小学校を卒業した安田少年は、親元を離れるために、自らの意思で、千葉にある全寮制の中学を受験して入学している。実はここでも安田はいじめに遭うなどして途中で退学・転校をしているのだが(その顛末は自伝に記してある)、千葉から安田が移り住んだのは再び神奈川、ただし今回は両親の離婚後、藤沢にある父方の祖母の家だった。
安田の少年時代を通じて言えることだが、生活の拠点となる家庭や住む場所自体がどんどん不安定化していった。
野宿していた公園
金沢文庫を離れ、藤沢方面へと車を走らせる。
『暗闇でも走る』には、彼が藤沢の祖母ともうまくいかず、夜の公園でベンチに寝転がって野宿をしていたという描写がある。私は、その公園に行けないものかと安田に聞いていた。
彼は「どこの公園だったか記憶が曖昧だ」と言いながら、Googleマップを使ってそれと思しき公園を探す。「確か駅の向こう側だったと思うんだけどな…」
「家の近くで寝ていると不審者だと思われるので、家から離れたところ、人気のあまりない場所を探していたと思うんです。何しろ金髪でしたし。背景が山というか森だったような映像のイメージは頭に残っているのですが、そこが具体的にどこだったのかはっきりとした記憶がなくて」
そんなことを話しながら、「駅の向こう側」に向かって高架下の道を走っていると、安田がふと「そういえば、この場所で友達が先輩にボコボコに殴られたんですよね」と言う。

「そうだ、まさにこの場所です。友達が先輩の彼女をバイクの後ろに乗せて、しかも転んでしまって。あとで分かったのですが、友達を殴っていた先輩も親が蒸発していたそうです。一体、何なのかなあと。その事件以来自分も先輩から目をつけられるようになったので、家に帰る時も表通りは通らずに、裏からまわり道をしていました」
見た目は金髪で強がっていたとはいえ、実際には気が弱かった中学・高校時代の彼の様子が伺える。当時の安田少年の居場所は、藤沢駅の改札前。手すりのところで何時間もたむろをしていた。

「何時間もこの手すりのところにいましたね。ここなら自分がいても大丈夫というか、ここにしか居場所がなかったとも言えるかもしれません。改札から知り合いが出てきたら声をかけたり。この銀の手すりに乗って知り合いとだべっていたんですよ。うんこ座りなら何時間でもできました」
そう言いながら、34歳になった安田も銀の手すりに腰を掛けようとする。両足の靴を手すりの下の部分に引っ掛けると、突然気づいたように「あ、でもこんなことしたら手すりが汚れちゃいますね」と素早く足を下げ、靴を乗せていた部分をいそいそと拭いていた。
「この改札も久しぶりに来ましたけど、やんちゃな子が全然いないですね。昔は自分みたいのが駅前に結構いたんですけど。自分が今、支援している子たちもそうなんですが、厳しい環境の子は増えているのに、社会からは昔より見えづらくなっているんですよね」
安田に一緒にたむろしていた友人たちとの仲を聞くと「当時は仲が良かったんですが、実は高校を卒業してから一度も連絡を取っていないんです」と答えた。少し寂しそうに笑っていた。

さて、再び「公園探し」に戻る。
彼が野宿していたはずの公園はなかなか見つからない。時間も経ち、そろそろ日が暮れる時間だ。Googleマップを見ながら「最後にこの公園に行ってみましょう」と安田。着くと、そこは駐車場があるような、とても大きい公園だった。
私は勝手に街の児童公園のようなものを想像していたのだが、むしろ代々木公園やキャンプ場の方に近い。池には鴨がいて、親子連れや老人たちが平和な時間を過ごしていた。
「ちゃんと思い出せないし、違うかもしれないけれど、でももしかしたらこの公園かもしれない。あ、あそこにベンチがある」

ベンチで寝たこと、背景が山だったこと。その記憶には当てはまっている。ただし、本当のところはわからない。何しろ20年近く前のことだ。
もしかしたら本当にこの場所なのかもしれない。安田しか知らないし、彼にだって確かには思い出せない。家にすら居場所がなかった、そんな時代の暗闇の記憶。
「街で普通に見かける子が、家や学校でひどい問題を抱えていることがある。そのことを知ってほしくて自分の本を書きました。自分の過去のことを書くのはとても難しくて3年もかかってしまいましたが…。でも、街でも公園でも、そう意識するだけで普段の風景が変わって見えてくると思うんです」

安田が言うように、貧困や剥奪の経験が広がるなかで、その存在はどんどん見えづらくなっている。皮肉なことだ。広がることで、見えなくなってしまったのだから。
しかし、広がっているのだから、実際には「見えている」のではないか。日常のそこかしこで、我々の視界を横切っているのではないか。
表面をそっとなぞるような視線では、心の中の暗いものまでは見通すことができない。でも、体の傷や、洋服の汚れや、髪型の変化や、笑顔の引きつりから、少年や少女の内面と周辺に起きている異変を想像することはできる。
いや、本当に、できるだろうか。
想像することが、できるだろうか。
「野宿していた話をすると、とても驚かれるんですが、自分にとっては普通のことだったんですよね。ケンカしたら野宿するしかないし、夜遅く帰ったら家の玄関のチェーンが閉められていたので。当時の自分にはそうするしか他になかった」
そう言いながら、彼は一つのベンチを選んでおもむろに寝転がった。4月初旬、日暮れ前の公園には、穏やかな風が吹いていた。

「ああ、気持ちいい。このまま眠れそうだ」
両親の不和、家庭内暴力、学校でのいじめ、不登校、引きこもり、うつ病。社会の中で少しずつ一般化していく様々な問題は、互いに連関し合い、その渦の中にいる者たちを苦しめ続ける。ニュータウン、校庭、高架下、駅前、公園、安田の少年時代はそうした「当事者」の苦い記憶で充満しているように思えた。
大人になった彼は、己の業に真正面から向き合うようにして「キズキ共育塾」をつくった。そうして、自らの問題を何とか飼い慣らしながら、自分以外の「当事者」たちの学びを支援しようとしている。当事者でない者たちへと、自らの体験を言葉で伝えようとしている。
「僕は自分が暗闇を“乗り越えた”という物語を書きたかったわけじゃない」
安田が口ぐせのように話していた言葉。その言葉が、自分の中に強い印象を残した。
彼はいまも、暗闇の中を走り続けている。
ほんの少しでも彼がまとう空気感を伝えられたらと思い、この短い文章を書いた。興味を持たれた方は、ぜひ彼の自伝『暗闇でも走る』を手に取ってみてほしい。
☆安田さんに「若者に伝えたい、挫折を乗り越えるために大切なこと」を聞いた記事はこちら!
その挫折は「物語」になる。困難を生きるすべての人へ
https://www.e-aidem.com/ch/jimocoro/entry/negishi29

☆この記事が気に入ったら、polcaから支援してみませんか? 集まった金額は、皆さまからの応援の気持ちとしてライターへ還元させていただきます。
『あの頃家にも居場所がなかった。公園のベンチで夜を明かした -「キズキ共育塾」安田祐輔の少年時代』(polca)