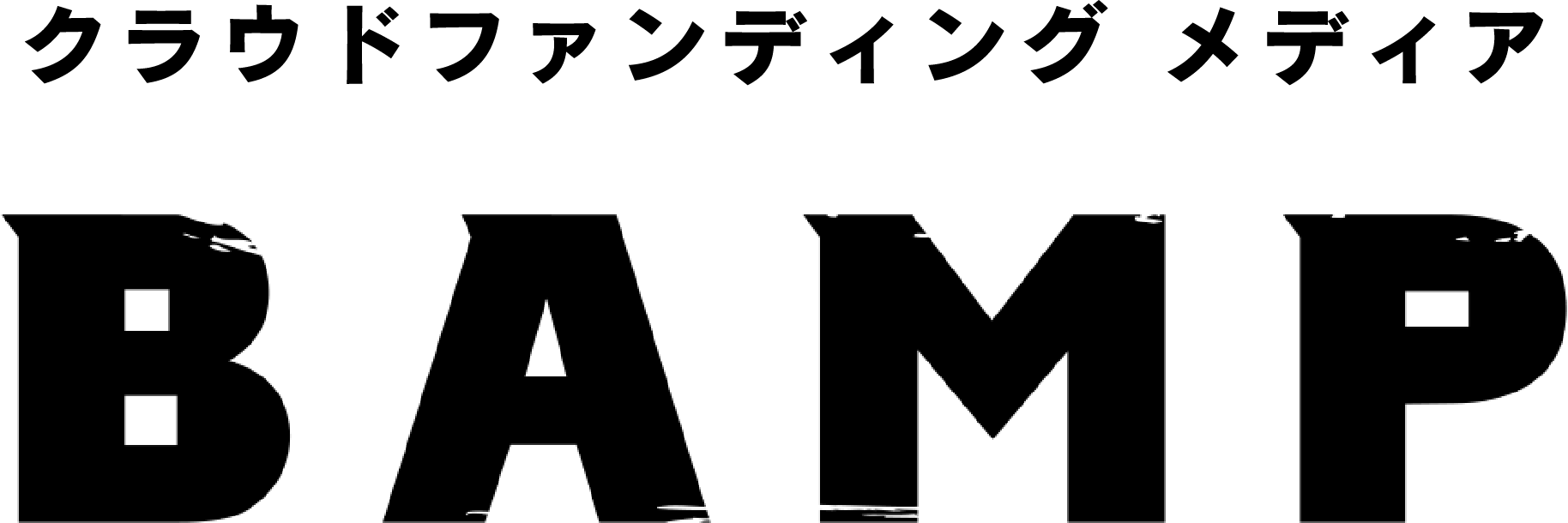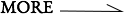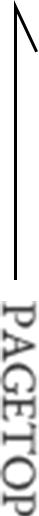たったひとりでリスクをとり、責任をとり、決断をし続ける人々、「経営者」。
彼らを見ているうちにふと気づいたことがある。
それは、わたしの中にも小さな「経営者」がいるということだ。わたしたちはみんな多かれ少なかれ、自分自身の経営者であり、自分の人生という事業を営んでいる。
世の経営者が会社から逃げられないように、わたしたちもまた、自分の人生からは逃げられない。鎧をかぶってこの平坦な戦場を生きぬかないといけない。わたしが経営者に惹かれるのは、きっとそれが拡大化・社会化された存在だからなのだと思う。

10月の京都の夜は、空気がだいぶ冷たくなっている。
今年初めて巻いたマフラーに顔をうずめ、街を歩く。
イヤホンで音楽も聴かず、スマートフォンを覗くこともなく、ひとり、ただひたすらに歩く。
京都の街を歩いていると、自然といろんなことが頭に浮かんでくる。
たとえば、自分にとって「孤独」とは何か?といったようなこととか。
これまで3名の経営者に話を聞いてきた『経営者の孤独』だが、「ここでいったんコラムを入れよう」と編集者に言われた。
「ここで一度『孤独』について、君の考えをまとめてみるのがいいと思うんだ」
「『孤独』についてのわたしの考え?」
わたしは少し尻込みしながら聞き返す。「孤独」について話を聞いてきたが、いまだにわたしはそれをきちんと言語化できていない。ただ、それがひとりひとりの中に確実に存在する、ということだけは、インタビューを通して体感してきた。
考え込んでいるわたしに対して、編集者はこう言った。
「まずは、君自身の『孤独』について書いてみてはどうだろう」
わたしは京都の街を歩きながら、自分の「孤独」について考える。
そして、これまでのインタビューで感じ取ってきた「孤独」のかたちについてを。

幼い頃からよく「さみしい」と思っていた。
何がさみしいのか、自分でもよくわからなかった。
そしてそれが、どうすればなくなるのかも。
「さみしくなくなりたい」というのが、幼い頃からのわたしの願いだった。
わたしの母は韓国人だ。
30歳で日本に来て、35歳でわたしを産んだ。
幼いころ、母はまだ日本語をうまく話せなくて、小学生に入るころには、わたしは母の言語能力を追い越していた。
よく母に言われたのは「あなたの言うことはむずかしくてわからない」ということだ。
わたしにも、母の話す韓国語がさっぱりわからなかった。
自分が成長するごとに、母に伝わらないことが増えていくのを感じるのは辛かった。
母に伝えたかった言葉はたくさんある。母からかけられたかった言葉もたくさんある。
だけど、わたしたちの間で言葉はあまり機能しなかった。
「さみしい」
それで、いつも簡単な言葉で伝えた。
母は、困っているような、悲しんでいるような顔をして黙った。
母がわたしをわからないように、わたしにも母がよくわからなかった。
不安、疎外感、寄る辺なさ、閉塞感。
今思えばわたしの「さみしい」のすぐそばには、いろいろな感情がひしめいていた。でもそれを言語化することも、吐き出すこともできなくて、ただ一身にそういった感情を真正面から受け続けていた。
なんだかずっと不安だった。ひとりだけ、外にいるような気がした。いつもどこかうすら寒いような、あとがないような心地だった。
「大丈夫だろうか」
毎朝目が覚めるたび、そう思う。
何を心配しているのかもわからない。とにかく不安で、さみしかった。
「大丈夫、大丈夫」
そして、自分に自分でそう言い聞かせながら、靴を履いて外に出た。

わたしが文章を書き始めたのは、小学4年生のころだ。
風邪をひいて数日休んだら、算数の授業が進んでいて、まったくわからなくなっていた。
今でも覚えているのだけど、その日黒板には「ヘクタール」と「アール」という言葉が書かれていた。だけどわたしには、「ヘクタール」と「アール」というものがどういったものなのかさっぱりわからなかった。
それらが面積の広さだということもわかるし、公式も理解できる。だけど、それらがどういったものなのかが感覚的にまったくわからないのだった。どれくらいの広さなのだろう? 一体誰が、どういうときに、何のために使う単位なのだろう?
まわりの子どもたちは、当然な顔をして問題を解いている。あるいは、解けなくてもそれがどうしたという顔をしている。誰も戸惑っていないし、恐れてもいなかった。ヘクタールとアールをきちんと受け入れていた。わたしだけがうまく受け取ることができず、どうすればいいのかわからないまま、途方にくれていた。
そのとき唐突に「ああ、自分はいつもこうだな」と思った。
夏休みの自由研究も、絵の描き方も、工作のつくり方も、作文の書き方も、調理実習も、友達との遊び方も、わたしはちっともわかっていない。教えられたら覚えることはできる。でも、それがからだにしっくりこないで、ぎくしゃくする。いつもどこか、おっかなびっくり生きている感じ。
まるで自分だけ、よその国から来たみたいだと思う。そして毎朝毎朝、目が覚めるたびにすべて忘れ、いちからやり直しになる。いつまでも馴染むことがないし、慣れることもない。常に緊張しながら、戸惑いながら、そこに立っている。
まだ10年ぽっちしか生きていなかったけれど、わたしはこれまでずっとそうだったということをそのとき自覚した。そして、きっとこれからもそうなのだろうと思った。
それは、すごくすごく、怖いことだった。
わたしはそのとき、消えてしまいたい、と思った。
こんな気持ちでこれからもずっと生きていくなんてことは、わたしには到底できない。
今、教室の窓から飛び降りて、消えてしまいたい、と。

4年生の教室は、4階建の校舎の4階にあった。
通っていた小学校には七不思議のうわさがあって、そのうちのひとつが、4年生の教室からは自殺者が出る、というものだった。
窓の外を見た瞬間、ふとそれを思い出して「あっ」となった。
自分がその七不思議の登場人物になったような気がしたのだ。
今わたしは、七不思議の物語の中にいるんだ、と思った。世界が反転したような、外から自分を見ているような、それはとても不思議な感覚だった。
わたしは、算数のノートに文章を書き始めた。
問題を解くことも板書を写すこともせず、しがみつくように書いた。
黒板の横に立つ先生、隣の席の男の子、立ち上がり歩き出すわたし、窓の桟にかけた足、ざわめく教室、飛び降りるわたし、流れる景色、ぶつかる地面。
わたしはわたしの目の前の世界を、次々に言葉にしていった。
現実には起きていなくても、それは「わたしの世界」だった。
これまで向き合ってきたどの世界よりも、ずっと自分に近しい世界。
わたしは書くことで世界に触れ、書くことで世界とつながっていた。
気がついたらチャイムが鳴って、算数の授業は終わっていた。
顔を上げ、教室を見渡す。クラスメートが立ち上がり、笑ったり喋ったりしている。
「助かった」とわたしは思った。いや、「助けられた」のだと。
あのとき、わたしは希望のようなものを感じた。
自分が自分の力によって、救われたような気がしたからだ。
「わたしはわたしを助けることができる」その方法がわかった気がした。
言葉を書くことでそれができるんだ。
他人に伝わらなくても、自分の言葉で自分を助けることができるんだ。
それがわかったのがとても嬉しかったし、心の底からほっとした。
逆に言えばそれは、「わたしはわたしにしか助けられない」ということを知った瞬間でもある。
あのとき初めて、自分の中の「孤独」に気づいたように思う。

それ以来、わたしは今に至るまでずっと何かしら書いている。
日記や手紙を始め、小説、エッセイ、短歌、ブログ、インタビューや対談記事……。
誰かに求められているからではなく、全部自分が生きていくのに必要だから書いている。
わからないことも、ひとつひとつわかることから書いていけば、いつかわかるようになる。
その瞬間、世界に触っているような気持ちがする。それが必要だから、書いている。
だけど不思議なことに、書けば書くほど「孤独」は深まっていっているように思う。
そして「さみしい」という感情、そしてそれにまつわる「不安」だとか「寄る辺ない」といった感情も、依然としてわたしの中に残っている。
わたしのイメージでは「孤独」は種で、「さみしい」は果肉だ。まるで桃のように、「孤独」の種に「さみしい」の果肉がしっかりと癒着し絡みついている。それは切っても切り離せない。種が大きくなればなるほど、果肉が接する面積も大きくなっていく。
おかしいな、と思う。
書くことで世界とつながってきたはずなのに、「孤独」も「さみしい」も消えないだなんてなぜなのだろう。
親友ができればなくなるのだろうか。恋人ができればなくなるのだろうか。
結婚をすれば、子どもを産んで母親になれば、なくなるのだろうか。
そう思ったこともあったが、決してそんなことはなかった。
誰と一緒にいても、「孤独」も「さみしい」も、わたしの中から消えることはなかった。
消えることはないのだとわかってからは、より一層濃くなっていった。
わたしは大人になっても何も変わっていない。
朝が来るたびさみしさや不安に溺れそうになりながら、大丈夫、と自分に言い聞かせる。あの頃と何も変わっていない。
変わっていっているのは、書く内容、それだけだ。
書くことは辛い。
「もう書きたくないな」と思うこともある。
「書かなくても生きていけるようになったら、どんなにいいだろう」と思う。
「いつか誰かが、わたしを助けてくれるんじゃないか」
そう期待してみるけれど、そんな「誰か」はいないということも、身にしみてわかっている。
結局「孤独」って何なのだろう、「さみしい」って何なのだろう。
大人になってもわからないから、やっぱりわたしは「書きたい」と思っている。
人に会い、対話し、感じ、思い、考え、また書く。
わかるまで書くしかないのだ。
だって、わたしにとって書くことは世界に触れることなのだから。これだというものをつかむまで、書くしかない。
それがわかったらきっと、自分の中で何かが変わるんじゃないだろうか。
そうした中でわたしは『経営者の孤独』というインタビュー連載を始めることになった。

鷗来堂・柳下恭平「プライベートとパブリックを分けられないことに僕の孤独がある」

クラシコム・青木耕平「正気でいながら狂うこと。 信用せずに信頼すること」

互助交通・中澤睦雄「だってしょうがない。ほかにハンドルを握る人がいないのだから」
経営者と話すのは、とても緊張する。
経営なんてしたこともないわたしが、「孤独」なんていう抽象的な大きなテーマをもって、どのように彼らと語り合おうというのか。
取材の前には眠れなくなるし、話をするときには手が震えたりもする。
だけど彼らと話していると、緊張すると同時に、すごくほっとするのも事実なのだ。
彼らは「孤独」を知っている。そして、それが自分を「経営者」たらしめているということも知っている。
わたしの中の「孤独」が、それに共鳴するのを感じる。そのとき、とてもほっとする。
これまで連載を続けて、ひとつだけ「孤独」についてわかったことがある。
人は、置いてけぼりになることで「孤独」になるのではない。
人は、進むことで「孤独」になるのだ、ということだ。
わたしが経営者と共通点を見出すならば、それは世界に触れようとしていることだと思う。
わたしが「書く」ことで世界に触れているように、彼らは「事業を行う」ことで世界に触れている。
世界に触れる条件は、自ら進むこと、そして「孤独」であることなのかもしれない。
「『孤独』って何でしょう?」
わたしは、まだ理解できていない。心が納得していない。
それで、緊張で震えながらも経営者に会いに行く。
彼らの中の「孤独」について、教えてもらいに行く。

三条大橋まで歩き、夜遅くまでやっているスターバックスに入った。
コーヒーを持って席に座ると、大きな窓の外に真っ黒い鴨川が流れているのが見える。
わたしは巻いていたマフラーをはずし、膝の上にかけた。
リュックサックに入っている本を取り出し、ソファに背をもたせかける。
隣の席から、男性と女性のふたり組が楽しそうに談笑している声が聴こえる。
窓には、わたしとそのふたりが浮かび上がるように映っており、遠くの方で、小さくファミリーマートの灯りがともっているのが見えた。
『自分ひとりの部屋』(※)と書かれた表紙をめくる。
「孤独」について考えようとしたときに、本棚から自然に選びとった本である。
イギリスの小説家のヴァージニア・ウルフは、この〈女性と小説〉というテーマのエッセイでこのように書いている。
「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」
女性であるということは、「孤独」のかたちに何か関係するのだろうか。
これまで男性の経営者に話を聞いてきたけれど、今、ぜひお話を聞きたいと思う女性の経営者がいる。
彼女の中にある「孤独」とは、どのようなものなのだろう。彼女はどのようにそれと向き合い、寄り添っているのだろう。
「いずれにしても、熱い議論になりそうなテーマを扱うときはーー性別についての問いはどれもそんなものばかりですがーー、真実をお話しできるなんて期待するだけ無茶というものです。どうやって自分がその意見を持つにいたったか、お見せするくらいしかできません。そうやって聴衆のみなさんに、話し手の限界、偏見、傾向を勘案しながら、ご自分の結論を引き出していただくしかないのです」
わたしは本を閉じ、コーヒーを飲み終え、席を立つ。
隣の席のふたりはすでにいなくなっていて、わたしは空っぽのソファを見ながらマフラーをまいた。
そしてまた、京都の街を歩き出す。
冷たい夜の空気が、頰をなでていった。

※『自分ひとりの部屋』ヴァージニア・ウルフ著/片山亜紀訳(平凡社刊)
☆この記事が気に入ったら、polcaから支援してみませんか? 集まった金額は、皆さまからの応援の気持ちとしてライターへ還元させていただきます。
『経営者の孤独/インターミッション「自分ひとりの部屋」』の記事を支援する(polca)
【お知らせ】本連載が2019年7月にポプラ社より書籍化されることが決まりました! 先行予約ができるクラウドファンディングを実施中なので、ぜひ合わせてご覧ください。