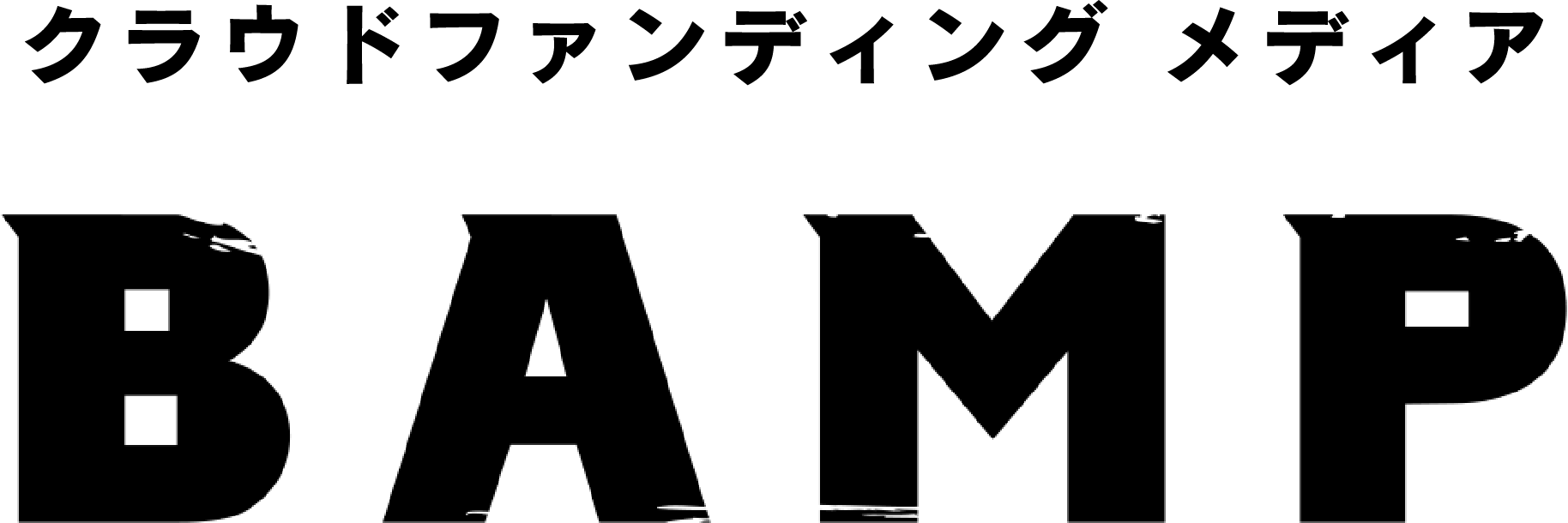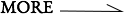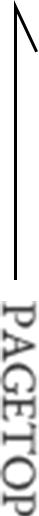「地方創生」
この言葉のもと、多くの地域で再生事業が進められている。
その一方で、常に直面する「空き家・空きビル」「担い手不足」「小学校統廃合」など地域特有の問題は日ごとに深刻度を増している。「地方創生」という言葉だけが一人歩きしているのではないか、と感じることも少なくない。
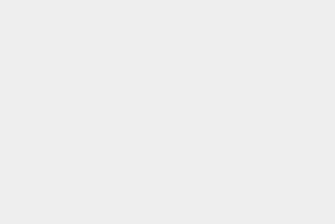
鹿児島県の北西に位置する人口2万人の小さな町、阿久根(アクネ)市もそうした地域のひとつ。その名の「アク」は、魚や漁業を意味する言葉、「ネ」は岩礁を示すのだという。古くから東シナ海の漁港町として栄えてきた。
僕は、人や自然に魅力を感じて鹿児島にIターンで移住してきた。お世辞にもまちづくりがうまくいっているとは言えない現状に漠然とした不安は尽きない。しかし、この阿久根という町には、次々と訪れる苦境にも意を介さず立ち向かう“勇者”がいる。
そのあり方は地方で不安にあえぐ僕たちにとって、小さな希望になるのではないだろうか。
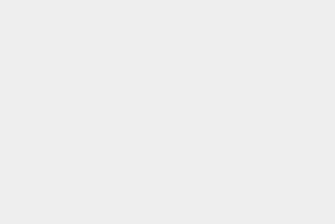
イワシを「丸干し」へと加工する下園薩男(しもぞのさつお)商店は、2019年で創業80年になる。地域との繋がりは深く、大きく掲げられた初代「下園薩男」の名からは、鹿児島の偉人〝西郷どん〟のように勇ましく人情深い男の姿が目に浮かぶ。
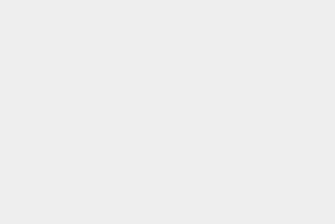
この店の3代目・下園正博さんが、故郷の阿久根へとUターンしてきたのは今から8年前。
東京でWEBディレクターとして勤めたあと、水産業の商社で営業マンとして優秀な成績を残しながらも、店を畳むつもりだった父の反対を押し切って家業に戻ってきた。
下園さんは2013年にウルメイワシの丸干しを世界各国の調味料と掛け合わせた「旅する丸干し」という商品を開発。干物文化の普及を図るこの商品のヒットがこの店の大きな転機となった。
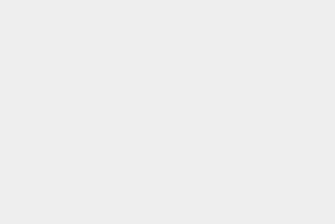
「旅する丸干し」全4種類。各800円(税別)。オンラインショップのほか全国20ヶ所以上で販売
下園さんはその「旅する丸干し」の成功をきっかけに2017年9月、市内の空き店舗が立ち並ぶシャッター街に、多目的施設「イワシビル」を立ち上げる。
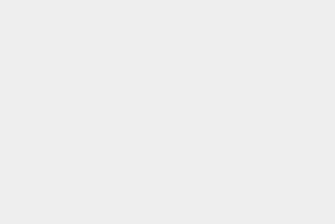
1階は、阿久根市を中心とした地域の特産品と工芸品の集まるショップとカフェ。2階は「旅する丸干し」の製造工程を見学することができる工場。そして3階は、海をモチーフにしたデザインの宿泊施設(ホステル)になっている。
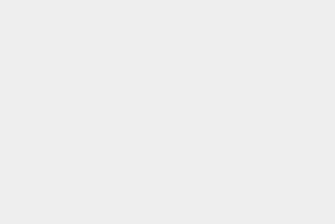
元々保険会社が入っていた空きビルをリノベーションした館内には、地域で使われていたものにリメイクを加えた品がところどころに配置されている。ソファーの鮮やかなブルーは阿久根の海がモチーフ
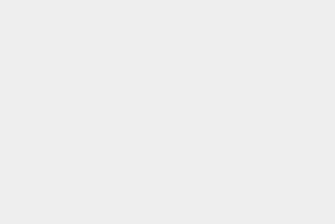
さらに、イワシビルではアパレル事業も展開。東京都墨田区にあるアパレル会社・和興と共同で制作したワークウェアも販売している。このワークウェアはイワシビルに関わるスタッフのユニフォームにもなっている。
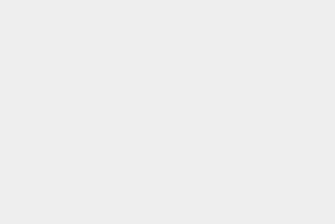
「大変なこともあるけど、嫌になって諦めたこととか全くないんですよね」と下園さんは笑う。
彼はなぜ華やかな東京の街から、故郷へと戻ってきたのか。そして次々と大胆な施策を打つことができる理由とは。お話を伺った。
家業をどうにかしたかった
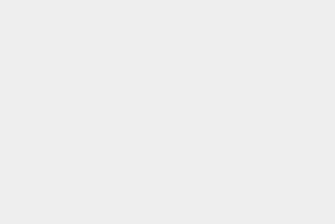
イワシの丸干しをオイル漬けにするというのは、かなり大胆に思えますが、この発想はどのように生まれたのでしょうか?
東京にいたときから、家業をどうにかしたいという思いがありました。20〜30年後には丸干しを食べる人がいなくなるかもしれないという危機感がずっとあったので。
でも、はじめはオイル漬けという発想ではなかったんですよね。普通に丸干しを若い人たちに食べてもらうために工夫していました。だから、丸干しのパッケージを自分で描いたりして。
下園さんご自身でデザインされていたのですか!
はい。イラスト寄りのパッケージにしたり、ちょっとおしゃれな名前に変えてみたり。バイヤーの評判は上々で店に置いてもらったりしたのですが、これが見事に売れなくて。
なるほど……その理由はなんだったのでしょう。
今まで買ってくれていたお客さんが「いつもの丸干し」がないからという理由で、買わなくなってしまったんですよね。「若い人に食べてもらいたい」というこちらの想いを一方的にぶつけても、それはお客さんには関係ないし、求められていない。意味ないなと思ってすぐにやめました。
そこからも試作は続けたわけですね。
そうですね。仕事終わりに事務所のキッチンで、勝手に丸干しを調理して、ずっと一人で実験していました。開発というよりも趣味みたいな感じですけど。
一時期は魚を取り扱うのを辞めた方がいいのかなとも考えましたが、魚自体に需要は必ずある、見せ方を変えるだけでいいはずだ、と踏みとどまって。
だからアプローチとしてまず考えたのは、丸干しを洋風にするということ。ただイワシの洋風料理というと、オイルサーディンしか思い付かなくて。じゃあいっそのこと干物をオイルサーディンにしたら面白いんじゃないかと。
とはいえ、オイルサーディンの専門書もなかなか見つからないので、料理本の中にある小さな記事を参考に挑戦してみたら、意外と美味しい。そこから本格的に試作品を作りはじめました。
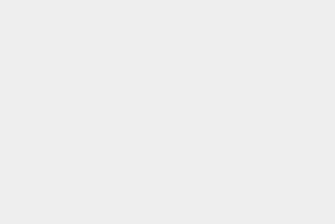
瓶詰めの商品にした理由はあるんですか?
雑貨屋とかオシャレな場所に置いてもらいたかったからですね。缶詰より、瓶詰の方が高級感もあるので。まあ、うちに缶詰用の機械がなかったこともあるんですけどね。
商品の反応はどうだったのでしょう?
イベントに出店した時に持っていったら、これまでの客層とは異なる20代の人たちや若い主婦の方が反応してくれましたね。
商品が違うにせよ、今まで198円で売っていたものの金額を一気にあげたので、売れるのか正直なところ心配だったのですが、売上もかなりよかったので、これはいけるかな、と。そこから本格的な商品開発を進める形となりました。
偶然が重なって生まれた「イワシビル」
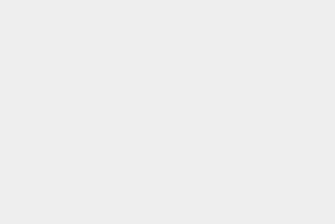
その「旅する丸干し」のヒットによって、「イワシビル」ができるわけですね。
そうですね。もともと自分たちで商品の説明をしっかりできるお店を作りたいと思っていました。「旅する丸干し」自体はいろんなメディアに取り上げて頂いたんですが、それだけでは売り上げは落ちていってしまうと思っていたので。ただ、このイワシビルに関しては割と偶然の産物というか。
偶然? どういうことですか?
ある時、父が町のビルが売りに出ているのを見つけてきたんですよ。ただ安いからという理由で買おうとするので、やめた方がいいと伝えたのですが、いつの間にか父が買ってきていて。
え!
父と話し合ったのですが、「お前が考えろ。何もしないならどこかに貸す」で終わりです。びっくりしますよね。人口2万人しかいないこの町で、駅から離れたビルを一棟買ってもどうしようもないじゃないですか(笑)。そもそも借りる人もいるかわからないですし。
確かに車がないと来られないような場所です。
だから、できるだけお客さんが来なくてもいいようにしようと。1階をショップとカフェにすることは決めていたのですが、2階は工場にして、空いた時間で1階のカフェスペースで事務作業ができるようにと考えました。
3階はホステルになっていますけど、これはどうして決まったんですか?
ちょうど悩んでいるタイミングで、市内にある大きなホテルの廃業が決まったんですね。そこで、京都にある「つくるビル」のリノベーションを手がけた石川秀和さんや東京・青山のスパイラル・チーフプランナー松田朋春さんに相談したら「1階から3階まで全部ホテルにしちゃえば」って言われて(笑)。
ホテルはさすがにやるつもりはなかったのですが、〝宿泊〟というキーワードはアリだなと。簡易宿泊施設だったら若い方も来やすくなるし、「旅する丸干し」の〝旅〟とも繋げることができる。ということでホステルにすることを決めて、石川さんにプロデューサーとして入っていただくことにしました。
1階がショップ・カフェ、2階が工場、3階がホステルという組み合わせは、全国を見回してもそうそうない。これを作っただけでメディアが来るぞって思いはありましたね。
確かにユニークな組み合わせなので、メディア受けは良さそうですね。
はい。だからオープンする前から『ソトコト』の表紙を飾るってスタッフに断言してたんですよ。実際、オープンして半年後には、編集長が遊びに来てくれて。「これは表紙になるぞ」って喜び勇んでいたら、実際は別のものでした。とはいえ6ページも掲載してくれたので、とてもありがたかったですけどね。
地元で流行るだけの店ではなく、東京にもない店を
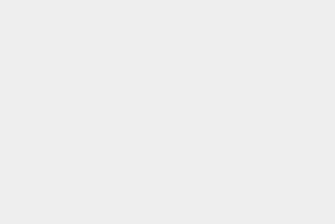
これだけの話題性があれば、かなり収支的にも見込めるのかなと思うのですが、実際のところはどうですか?
下園薩男商店としての全体売上で、イワシビルからの収益はまだ約1割ほどですね。
リノベーションに借金5000万円かけているので、その返済も考えると月単位の採算としては、トントンという感じですね。
5000万円!
鹿児島のデザインを底上げしたいという想いがあったので、手を抜いてはいけないなと。おかげさまで、デザインに目の肥えた東京の人たちからの評判も悪くないです。
地元の人からの反応はどうですか?
もちろん褒めてくださる方はいるのですが、鹿児島って、東京で流行している「それっぽい」感じのメニューやデザインの方が圧倒的に流行るんです。うちも当初はポートランド系の内装で、アメリカ製のパイプ椅子を使うことなども検討しましたが、それは辞めました。そういうのはあんまりやりたくない。
やりたくない……ですか。
流行を追いかけて二番煎じになりたくないからです。むしろ、東京にないお店を作りたいと思いました。何より下園薩男商店の理念でもある「今あるものに一手間加え、誇り楽しみ、人生を豊かにする」を大事にしたかったので。
だから、代々受け継いできた歴史と「旅する丸干し」の二つを軸にして、内装のテーマを「時と旅」にしました。干物用に使っていた台を再利用したり、コンテナを材料にしてソファーを作ったり。生活の中で利用していたものに一手間加えたものを置くようにしています。
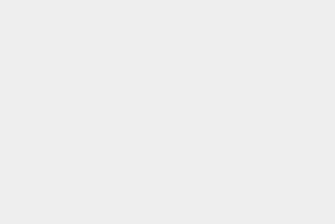
一方でアパレルなど新しい取り組みもされていますね。
もともと、スタッフ用の服を作りたかったんですよね。というのも、工場の服ってマスクをはめて、身体中を覆って、と機能が優先されすぎてしまって、どこも同じような服装じゃないですか。確かに食品会社として、安心安全が一番大事なことだけど、「それって本当に幸せなのかな?」と思ったんですよ。
だから衛生的な基準を満たしつつ、スタッフがプライドを持って働けるデザインの服を作ることにしました。味気ない作業服で仕事をするよりも、誇りをもって仕事をできるような制服の方が、製品もサービスも間違いなくクオリティは上がりますよね。やっぱり身に付けるもので心の持ちようって変わると思うので。
そこで、和興さんと仲良くなった時に相談をしたら、是非協力したいと言ってもらえて。アパレルに関しては、そこからですね。
億万長者もレベル99もきっとつまらない
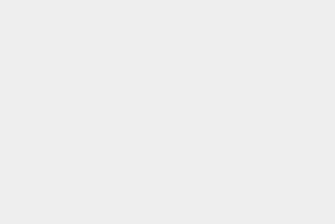
「イワシビル」や「旅する丸干し」など様々な施策を次々と進め、着実に歩を進めている印象です。しかし、お店を継ぐことに対するプレッシャーなどもあったのではないですか?
実はそういうの、全くないんですよね。鈍感なのかな。色々言う人はいるのかもしれませんが、あまり人の言うことを気にしていないのかもしれません。
なるほど。ただ金銭面など、現実的に直面する厳しい問題などは多いと思うのですが……
実はゲームがすごく好きで、小さい頃ずっとやっていたんですよ。そのことが今にすごく生かされている感覚があって。
ゲームですか。
はい。『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』の発売日には、学校をずる休みして買いに行って、ご飯の時以外はずっとゲーム。クリアするまでは学校も一週間くらい休みっぱなしでした(笑)。
それはすごいエピソードですね。
ですよね(笑)。当時はとにかく早くクリアしたかったので、いかに効率的にやるかということばかり考えていたんです。
たとえば、まず朝起きた時に今日はゲームを何時間できるか、という想定からはじめるんですけど、すると、この時間までにキャラクターのレベルをここまで上げなければいけない、となるわけです。そこから効率よく経験値を貯めるためには、この武器を買わなければいけない。そのためにはお金を貯めなければいけない。と、どんどん目標設定がされていく。
効率を上げることなんて、当時は小学生なので誰にも教わったわけではないんですけど、とにかく好きなことだから、自ずとそういう方法を学んで編み出していくんですよ。
確かに当時ゲームをしているときは自ずとそういう選択肢を取っていた気がします。
結果として、勉強を全くしなかったのに、やたらと数学の成績が良くなった。今の生産工程にも繋がってきている感覚もあります。いかに効率的に難しい問題を解決するかという感覚ですね。
ただ、ゲームをしていると気づくと思うんですけど、レベルがMAXになって、敵がいなくなった途端につまらなくなるんですよね。わからない問題に対して、試行錯誤している最中が一番楽しいわけです。
それって多分ビジネスにおいても一緒で、きっと億万長者もレベルMAXもきっとつまらない。
ならば、実家を継ぐことで自分の使命を全うしたいなと考えました。やっぱり長男でしたし、自分の幸せや、自分にしかできないことに向き直った時に、それが一番だと思ったんです。
私が学生時代、うちの父は会社を自分の代で畳むと言っていましたが、それは勿体ない。確かに地域には問題は多いかもしれないけれど、地域づくりも『シムシティ』みたいなものとして考えれば楽しめる。トラブルがないゲームなんて面白くないじゃないですか。
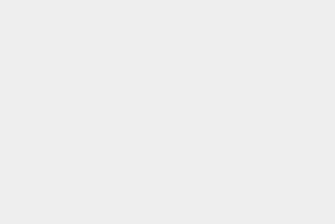
楽しむという言葉がキーワードになっていますね。
正直、楽しくしないと、やっていけないところもあるんですよね。
下園薩男商店は80年続いているので、私のものじゃないんですよ。うちの祖父が作って、従業員が働き、それをうちの父が継いで、その歴史が積み重なったのを私が背負っているんです。
それに、地域の企業から資材も頂いているし、阿久根の漁師さんから大量にイワシを仕入れている。もしうちが潰れてしまったら、私たちだけではなく、地域の人たちの暮らしまでどんどんと追い込まれていってしまう。
これだけの責任を真っ向から全て背負おうとしたら、すぐに潰れてしまいますよ。でも楽しむことができれば、色々と試行錯誤をすることができる。それがRPGの“勇者”から学んだことなんです。
どこにいったとしても、何をやったとしても、絶対に壁にぶち当たる時がきます。その壁を乗り越えられるかどうかは、そのことが好きかどうか、そしてその状況を楽しめるかどうかなのだと思います。
下園薩男商店オンラインショップ
- 鹿児島県阿久根市で食品を中心に扱う「下園薩男商店」のオンラインショップ。昔ながらなものに一手間加え、これから何十年、何百年その地域に伝統や文化を残すことに取り組んでいます。
- https://maruboshi.thebase.in/
☆この記事が気に入ったら、polcaから支援してみませんか? 集まった金額は、皆さまからの応援の気持ちとしてライターへ還元させていただきます。
『「地方にゲームオーバーはない」イワシの干物を巡る旅が、老舗の三代目を“勇者”にした』の記事を支援する(polca)